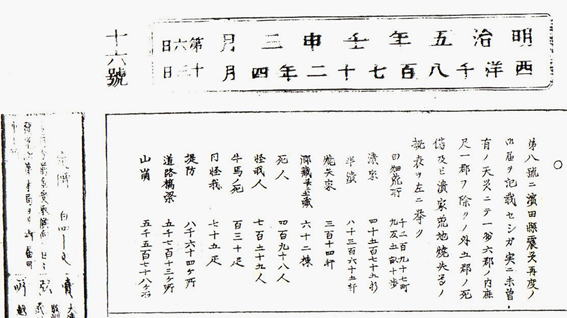�@�u�E�c���Y���c�����@���{�̏h��v
�@�@�@�@��O�́@���c�����\�@�@�@�@�@�@���̂Q
�@�@�@�@�@�@���̐ߋ�
�a�@�̒�ɔ~�Ⓧ�̉Ԃ��炫�A�������������Ȃ����B
�����́A���O�̒��q���ǂ��������B
�u��������A�����ɂȂ�܂��H�v
�u�������ȁA�ӂ������v
�u��������ł���B��������������Ă�������Ȃ��E�E�E�m���A���ɂ���܂����ˁB�����l�̔����v
�u�����A����A����B�̂̕����B�悭�m���Ă���Ȃ��A���O�́E�E�E�������A���O�͂悭�����ꂽ����Ȃ��A���ɁB�͂͂́v
��u�A���O�����Y���m���ʉe���h�����B
�u�e���͕|�������A�{�����I�v
�u�͂͂́B���O�͂悭����ꂽ����ȁv
�v���U��ɌZ��ŏ����B
�u�e���͂ǂ����Ă��邾�낤�H�v
�u�������Ȃ��B�܂��A���v���v
�����͌��������̂̐S�z���B����̑��q����l�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B���������Đf�Â��n�߂���������Ȃ��B���O�������v�����낤�B
���������A���̂����l���C�ɂȂ�B���N�͖Z�����ď���Ԃ��Ȃ������B���N�͋Q�[�ł���Ȓi�ł͂Ȃ������B���N�͂ǂ��������ȁH�@�Ȉ�l�ł́A������o���Ȃ����낤�Ȃ��E�E�E�B
��Ő�������Ă���ƁA�N�I�搶���������ɂȂ����B
�u���͂悤�B���O�͂ǂ����H�@�܂��܂����H�v
�@���͐���Еt���āA���O�̕����}�����B�搶�ƌ��O�������b���Ă���B�������A���̑����ɋC�t���Ă��A�b���~�߂��B
�@�����Č��O���A�ɂ킩�ɊP���n�߂��B�w�����C���Ă�邵���Ȃ��B�܂����A���O�̎�������^�����Ȍ����������B
�@�搶���������ĊO�ɏo���B
�@���O�͐搶�ɁA���������ɋA���ė~�����Ɨ��������B����͂����A�����̂��Ƃ��S�z���B�N�������q�ǂ������ō����Ă��邾�낤�B�������A����ȏ�Ԃ̌��O���c���ċA��Ȃ��B�A��ċA�邩�B
�������O�́A��w�������ĔM�S�ɓǂ�ł���B���Z�������̏��ђB���Y�N�������̂悤�Ɍ������ɗ��āA��܂��Ă����B�����ĒB���Y�N�ƁA�e�[�x�[���ǂ��̂����̂ƁA�h�C�c�ꍬ����Řb������ł���B�h�C�c��w�����~�̖]�݂��q���ł���悤���B���̋C�����͒ɂ��قlj���B�����ɋA�낤�ƌ����Ă��A����Ƃ͌���Ȃ����낤�E�E�E
�@�����̂悤�ɁA�N�I�搶���炨���������������B�ς݂܂���ƌ����Ď��ق��Ȃ��B�����ɋA��ƁA���ɂ��ĂƖ���������B
�@�]��̎R���N�����ܓ��u���Ɍ������Ă����B�����āA�㋞�̍ۂɎ��Q�����������Ă��ꂽ�B�����ɒ���������ς肪�Ȃ��������̍��z�́A�Ƃ��ɒ��˂��Ă����B
�@�@�@�@�@�����Ȃ̍��Y�N
�[�֏��̂��Ƃŏ����Ă��ꂽ���Y�N���A���̐����ɕ����Ȃɍ̗p����A�ҏS���ɋΖ��ƂȂ����B���Ɠ����ێR�����~�������ɏZ�݁A���������ʂ��B�ȗ��A����̂悤�ɔނƘb���B
���Y�N�͈ېV�̑O�A���̒����~�����������E��w���A���������̊J�����ɒʂ����B���̍��̐�y�������O�V�Ƃ����o���ˎm�������B���̕��͓ƌ���w�����A���Y�N��������w�B�����A�����O�V�搶�͑�w������Ȃ�A�c���֊w����u�������u�����߂�������B���̌���A���Y�N�������̋�����������Ă��邱�Ƃ�m���Ă���ꂽ�悤���B���̂悤�ȉ����A���Y�N�������Ȃɍ̗p���ꂽ�炵���B
�u�����搶�����������ɁA�����������ɗ����x�ꂽ�B��������M�ɕ�������A�܂Ƃ܂肪�Ȃ��������炾�B���傤�Ǔ��{���A���{������ɕ�������������悤���E�E�E��������������I�����������擪�ɗ����A��M�𗦂���������N�A�����푈�ɏ������B�����Ɋw�ԂƂ��낪�傫���Ƃ����������v
�u���{�������J���œ��ꂵ�����ƂɊԈႢ�Ȃ��ƁE�E�E�v
�u�����v
�u���͂��ꂩ�炾�B�o���o���ł͍���B���{���͂����킹�āv
�u�����E�E�E�������A�����̋���͍������ė�M�Ńo���o���B���̓_�A�����̋��琧�x�������Ă���Ƃ��������v
���Y�N�́A�����̋��琧�x�ɂ��Ė�{���o���������B
���̑��A�O���̋������ɂ��Ă��낢��Ƌ����Ă��ꂽ�B
�@������u���ӂ́v�ƌ����āA���Y�N�����̕����ɂ���ė����B
�����āA�u���̐V���A����`�����A�܂��I�v�ƌ����āA���������V���̑n�������������B
�u���`�����A�܂��H�v
�u�����ł��B���R�˂̍]�ˋl�Ȃ�A���`����m��Ȃ��҂͂��܂����v
�u�E�E�E�v
�u���`���́A�㉮�~�ɏo����̌������ł����B�Ȃ��Ȃ����˂�����l�ŁA���O���ɔF�߂��ĕ������ɂȂ�܂����B�ȗ��A���̓��Ő����A�炵�����̂ł��v
�u�E�E�E�v
�u���̓`�����A�w�]���V���x�Ƃ����V�����o���܂����B�撣���Ă������A�ېV�ɂȂ��Ď~�߂������܂����B���{���Ƃ����̂Łv
�u�E�E�E�v
�u�Ƃ��낪�A�ق�A���̓��������V���B�����Ɂw�]���p�k�x�Ƃ�����������ł��傤�B������Ǝv���ĕ����Ă݂���A��͂���`���ł����v
�u�E�E�E�v
�u���s���̐������֍s���Ă�����Ă��܂����B�����A�o���ƈӋC����ł��܂����v
�u�����H�v
�u�����I�@������w�����x�ƌ����̂������ł��E�E�E�����A�o��V�����Ȃ��悤�ł́A�̒��ԓ���͂ł��܂���v
�u����Ȃ��̂��H�v
�u�����B�������ɂȂ�ɂ͕K�v�s���ł��I�v
�@���Y�N�͎��M�����Ղ�Ɍ������B
�u���������A�\�����m�点�Ă����B�č��ł́A�������������Ƃ������̐V���ɍڂ�B�e�����s���T���t�����V�X�R�ɒ�������A�����̐V���ɍڂ����Ƌ����Ă����v
�@�ؒ��{���o�e�����s�ɐ��s���ēn�Ă����\�삪�A�j���[���[�N�ɗ��������܂ł̋I�s����˂֑����Ă����B
�u���́A�ǂޑ��ł��B�ǂꂾ���̐l���V����ǂ߂邩�H�v
�u���̒ʂ�E�E�E���c���v�搶�́w���m�����^�x�ɂ́A�p���l�͒N�ł��{��ǂ݁A�N�ł��V����ǂ�Ŏ����̗ǂ�������]�_����Ƃ������v
�u���{�l�͉������ǂ߂邾�낤�H�v
�u�����ł͂��Ȃ�̐l���ǂ߂邾�낤���A���R�ł́E�E�E�����ł́E�E�E�v
���Y�N�ɑ��k���Ď��{�����������̑�c�l�I���ŁA���O��������҂͌ˎ�̎l���̈ꂾ�����B
�u���̂����A�[�֏��Ŋw�q�ǂ�����l�ɂȂ�E�E�E�v
�u������B������A������[�֏�����Ȃ̂��I�v
�@���x�́A�������M�����Ղ�Ɍ������B
�u�������A�V�������ɂ͂������v��B�ꖇ�S�l�\���B��J������\�ځB�n�R�l�͎��Ȃ��ȁv
�@�����������Ȃ炴��Ȃ������B
���̍��A���Y�N�Ƙb���x�ɘb��ɂȂ�̂��A�����ƕ��R�A�����đ��Y�N���m���Ă��鈾�����Ƃ̊i�����B
�u�����͂����܂����B������ɗ��Ă�����A�ǂ�ǂ�ς��v
�u�E�E�E�v
�u�������H�V���X�e���V���I�v
�u�����A�w�ɂ�ԌɁB�������͂��ׂēS�ŁA�p������̗A�����������ł��v
�@�p���͗L��]��قǂ̓S���Ă���ƁA���c���v�搶��������������B�������{�ɂ܂ŗA�o���Ă���̂��B
�@���Y�N�͐��{�̂���l���B��������ē����Ă�������������B
�u���H�̍H���������ɐi��ł��邻���ł��v
�u���H�̐�͊C��n���āB����͑�H�����I�v
�u�p�n���ł��Ȃ��������߂炵���ł���v
�u������g���Ă���ȁv
�u�������p���̐��b�ɂȂ��Ă��邻���ł��v
�u����Ȃ��Ƃ܂ł��āI�v
�u�˂̎؋��̌�����ŗ\�Z���Ȃ��Ƃ��v
�@�������������h���B���������Ă�����Ȃ�������B
�u���ꂩ��́A�������{�ɏW�܂�܂�����B����Ăɂ��Ă���̂ł��傤�v
�������A�ŋ��͂��ׂĐ��{�ɏW�܂�B�ŋ������̂��g���̂��A���{�̎v���̂܂܂��B���ꂪ�p�˒u���Ƃ������Ƃ��B
�u�E�c����B�ǂ�������܂����H�v
�u���[��B�܂��A�����������Ƃ��ˁv
�u���{�́A�܂��܂����C�ł���A�V�������Ƃ��v
�u����������ł́A�܂�����V�����I�v
�u���V���H�v
�u�������B�V���̍��V�����A�������B�������̂������������������B��X���m��Ȃ��������B����Ȃ��Ƃ�����A�d�M�@�͖��@���A�ِl���������炤�������đ������N�����v
�u�����B�ł�����A�����̂Ƃ�����ǂ����邩�ł��v
�@�˂̎���Ȃ�A�˒��֍s���Ηǂ������B���{���ƁA�ǂ�����B�������������܂ŗ���̂��B
�u�́A�ǂ����Ă���H�v
�u���ɋc�����܂��B������c�����o���B�����Ȃ�A�e�������b�����c����B�p���Ȃ������ցB�č��Ȃ��������ցv
�u�E�E�E�v
�@���������A���c�搶�̂��b�ɂ������B
���̐Α���̑吭�c���ցA�S���e�n����c�����E�E�E�B
�u�����āA���̋c��ɂ͌S����A�S�̋c��ɂ͑�����c�����o���v
�u�Ȃ�قǁB���̂悤���q�����A�����ӌ����肢�������A���{�ւƓ`���v
�@������S�ցA���ցA���{�ւƘA�ւ���B
�@�b���Ă���ƁA���ђB���Y�N������ė����B�B���Y�N�́A�߂������ɕ��R����ȂƖ����Ăъ�B���Y�N���A�Ȃƒ���Ăъ�B�b�͎؉Ƃ̂��ƂɂȂ����B��l�Ƃ��O�r�m�X�E�E�E��l�̐��͒e�B
�@�@�@�@�@�@������
�����ܔN�O�����{�B
���Y�N���A��������ςɍs���Ȃ����Ɗϗ��������ꂽ�B
������͕����Ȕ����ǂ̎�ÂŁA�����̐����̑听�a�ŊJ�Â����B
���͒��������炲�����Ԃ��Ă����B
���ʂ̑听�a�⍶�E�̘L���ɁA�W���̒I��K���X�̔��B��w��Z�̕��Y��̎����𒆐S�ɁA�c�����䕨��×��̕������A�L�O���A�y��A�D�z�A����A�؍H�i�A�S�⓺�̓���A���ށA�ʕ��A�z�A�����̕W�{�A�����̕i�X�A�����a�т̋@�B�Ȃ��A�Í��̒������������ƕ���ł���B
�@�����̎Q���ɐl������B�\�̋��������B�u�������É��͏�Ŏ��v�ƉS�����A�������É�������������W�����Ă����B�����ٗl�ɑ傫��������������B�����悤�ɐ����̂�����l������ł����B
�@�ϗ��q�̘b�����ɓ������B
�u�������������Ƃ����b���v
�@���̓����O�Ƃ̔����˂��A�V��t���͂��Ɍ��シ��B
�唻���疇������Ƃ����b���B�����˂ɂ����z�Ȕˍ�����͂������E�E�E�B
�@�Ȃ�ƁA�R�������W������Ă����B�傫�����̒��ł����Ƃ��Ă���B�����ɂ͑�R���邪�A�����ł͒������̂��B�a�����m����炪�����~�܂��āA�s�v�c�����ɊςĂ����B
�s�������l�̕����͘a���ɗm���A�����̐ܒ��^�B�����A�����ɌC�B���^�������ɂ������A�V�哪���U�������B�唪����l�͎ԁB�l�������A��b���������B
�@�@�@�@�@�@���O���c����
�@�����炫�A�߂�����g�����Ȃ����B�������A���O�̕a��͐i�ވ�����B�H�~���Ȃ��B�������葉�����B�p�ɂɊP���݁A�[���ɂ͔M���o��B�Q����~���̂ŁA�āX�A������������B�����\�����邩������Ȃ��B
�ێR�@�̂����~�����������}�������A�����͔ˎm����l�����A��l�������Ă�������₵���Ȃ����B���ђB���Y�N�����Y�N���A�������o�ĐV���ֈڂ����B���ɂ́A�b��������������Ȃ��B�a�@�Ɖ������ĂЂ�����Ō�̓��X���߂������B
���̍�����A���O�͒��ځA���ɁA�����ɋA��ƌ����悤�ɂȂ����E�E�E��t�s�݂Ŗ��f���|���Ă���B�������o�鎞�ɑ�R���S���������������B�����̊F����ɐ\����Ȃ��B�e���������Ă��邾�낤�B
�������Ō����ĊP���݁A�������肷��B
�@�N�I�搶�́A�u���O�������悤�ɂ��Ă���Ắv�Ƃ��������B�u����Ȓ��u���ċA��ȂǁA�ƂĂ��ł��܂���v�ƌ����ƁA�搶�́A�u�l�̋C�����ɉ����̂��l�̓����v�Ƃ�����������B
�@���H���o���B�������A���O���ϕ�������t���悤�Ƃ��Ȃ��B
�u���O�A�H�ׂ�I�v
�@�ƌ����ƁA���O���A
�u�Z����A�����ɋA���āI�v
�@�ƌ����B
�u�H�ׂ�I�v�A�u�A���āI�v�A�u�H�ׂ�I�v�A�u�A���āI�v
�����ⓚ���Z�������ɂȂ����B�����Ă����A
�u���������B���������B������������H�ׂ�I�v
�ƌ����Ă��܂����B
�@�N�I�搶�ɉ��߂đ��k�����B
�N���́A�����̏f���Ǝ莆�̌�����������悤���B�N���͗ܐ��ŁA���������O�̖ʓ|������ƌ����Ă��ꂽ�B���ђB���Y�N�⍲�Y�N���A�v�w�Ő��b�����Ă����ƌ����B
�@�Ƃɂ����A��U�A���R�A�낤�B�䂪�Ƃ��S�z���B���c��Q���ɕ��邱�Ƃ�����B�p�˒u���ŕ��R�͂ǂ��Ȃ������B�[�֏������܂������Ă��邩�B���R�˂̔ˎD�́A���܂��ɐV�����Ƃ̌����䗦��������Ȃ��B���։�Ђ͂ǂ��������E�E�E�B
�v�����āA���O�ɕʂ���������B
�u�p�����I�������A���N�̂����ɂ܂�����B����܂łɌ��C�ɂȂ��āv
�@���ꂪ�����̕ʂ�ɂȂ邩������Ȃ��B���O���͂�U��i���āA���ւ܂Ō������Ă��ꂽ�B���Â��L���ɗ����O������A�������|�������B
�@�@�@�@�@�@�ł̖���
�@���˓�������B
�D�̌���������������P���A�قǂȂ������ɏ������B���̒������_�ɉB�ꂽ�B
�O����\�l���̒��A�グ���ɏ�����ۂ̉Y�ցB
���������������v���o�����B
����o���̃I�����_���و�̃V�[�{���g�́A���ْ��̍]�ˎQ�{�ɐ��s�����ۂ̍`�֗������A�y������L���ɔ������B���̐܂ɃV�[�{���g������w�̂��Ƃ�b�����̂��낤�B������́A�ۂ̈�Ғ��Ԃ���V�[�{���g�̂��Ƃ����B���Ƃ��Ɗ�����̕�������ɍs���C�ɂȂ����̂́A���ꂪ���|���������B
����ɂ��Ă��A���Ɍ��O�̂��Ƃ��ǂ��b���悢���A�㗤��O�ɂ��ċC���d���B
�@
�@���M�ɏ�芷���č`�ցB
�D���Ɍ������������������ɉ��������B�D�����������ނƁA�ق��Ƃ����B
�@�������Ɏg���𑖂点�A�ҍ��ň�x�݁B
�@�������ɁA�}�����l�l����Ă����B
�@���J���U�钆�A���낼��Ɠ��₩���ۊX��������B
�ۂ́A�����炩�ς�����悤���B�������A��鉺�͐̂̂܂܁B�o���O�ƕς���Ă��Ȃ��B���������N������A����Ȃɕς��͂����Ȃ��̂����A�����̓��X�ς��s���L�l�������̂ŁA�]�v����������B
�s�������l�̓����╞�����̂̂܂܁B�H�D�����A��ɓ��B��Β��J�ɂ����V����B�����s�x�A�����̒N���Ǝv���Ă��܂��E�E�E�����ł́A���ʼn���Ă��m����B���т��тƖZ�������ɕ����B�܂�Œ��q���Ⴄ�B�����͐����A�c�ɂ͒��B���̂܂܂ł́A�i�����g������肾�B
�p�˒u����̂��Ƃ́A�����ŕ������B
���R�˂͕��R���ɂȂ�A�Ԃ��Ȃ��A��J�NḐ搶���c�䕽�����̔����ƈꏏ�ɂȂ��Đ[�Ì��ɂȂ����B�����Č���������̏��c�S�}�����Ɉڂ����B
���R���������B��傪���Ȃ��Ǝv���ƁA�������т��鏼���������B�u��t�ɂ��������[���v�Ƃ͂��̂��Ƃ��B
���͂Ƃ�����A���c��Q���֕��Ȃ���E�E�E
�O�̊ۂ̋��˒��̓K�����Ƃ��āA���l���ڂ���Ƃ��Ă����B���c��Q���͊}���̌����Ŏ������B�[���ɂ͋A����Ƃ̂��ƁB
����܂łɁA�]���k���搶�֕��悤�B
�]�ؐ搶�̂����K�˂��B�搶�̂���́A���V�ق̐^�������ɂ���B���̔ˍZ���V�ق́A�p�˂̂��ߑ�������Ԃ܂�Ă���B��̑O�͐l�e���Ȃ��A�S�Ȃ����₵�������B
�]�ؐ搶�͌�ݑ�����B
�u�������A�A��܂����v
�u���A���A���E�E�E���J�ł������B�オ��A�オ��v
�q�Ԃɒʂ��ꂽ�B
�u�ˎD�̌��͉����Ɏ��炸�A�\����܂���v
�u���₢��A��Q�����畷�����B���D�͖��͂��B����̑Ώۂ���O����Ă��v�����Ȃ��Ƃ���B�x���͂Ȃ邪�A�����������Ă��������邾�낤�B�N�����̂��A���B���ꂩ����S�苭���呠�Ȃւ��肢���āv
�@���O�̂��Ƃ�b�����B
�@�t�̑O���B�N�b�����Ȃ��A���ŗ܂�@�����B
�@�]�ؐ搶���A���炭�����Ȃ������B
�u���Y�N�B�N���C�����������Ȃ���E�E�E����������҂��̂��Ƃ��낤�v
�u�͂��B���肪�Ƃ��������܂��v
�u���₠�B���������ς������B�����Ă��邾�낤���A�ˎm���ł���Ă������ɍ����A�Ƒ��ŏ�֓������҂�����B�\����̉Ƃ���Ȃ��Ƃ��낾�����B�����ِl��A��ė��āA�d�M�@���������B�ƂɉB��Ă���ɈႢ�Ȃ��B������Ɨ����������o�����B�ߏ��̎҂��A����Ȃ͂��͂Ȃ��B��͍��A�Z�痢���ޕ��ɂ���ƌ����Ă����Ƃ���֕��������ď��������v
�u���Y�N�������Ă��܂����B��̊O�ŗ������A���̉Ƃِ͈l�̊w���������B�Ă��Ă��܂��Ƌ��Ԃ̂����B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��A�������S�n�����Ȃ������Ɓv
�u���������B���̘b�����m�w�҂́A�}���Ŗ���\�D���O�����B�������̂Ƃ���Ɏg�����o���āA�\�D���O�������v
�u�E�E�E�v
�u�ȗ��A�鉺���l����肾�v
�u�����A���̔˒��͎₵�����̂ł����v
�u���߂́A�����Ɍ��������������E�E�E�����ˎm�̉��~�Ɏ��͂܂�āA���ɂ����Ǝv�����̂��낤�B�ˎm�͘\��������A�E���Ȃ��A�����Ă���B���N�ɂȂ��āA�����͔����̊}���Ɉڂ��ꂽ�B���S���Ƃ������������ɂ��v
�u�E�E�E�v
�u�}���̌����ɂ́A���{�I���̊������ǂ�ǂ荞�܂�Ă���B�R�����A�啪���A�u�����A��ʌ��A�����{����E�E�E��������ɔ����Ă���ė����������̎m��������v
�u���R�˂�����H�v
�u����B�����Ƃ����Ɗ����Ɉ������ĂĂ��������Ȃ���B�L�\�Ȕˎm����R����̂�����v
�u�E�E�E�v
�u���̂Ƃ���A��̔ˎD�̎��Ԃ������Ă���B���{�͕��R�˂ɗ�W���B���c��Q�������̂悤�Ȃ��ƂŁA���{�Ɋ|�������Ă��A�v���悤�ɂȂ�Ȃ��v
�u�č��֓n�������N�������N�����{�ɏA���Ă����v
�u�����҂��Ă͂���Ȃ��B�Ƃ������ˎm�Ɏd�����E�E�E���������l����A��āA���ێR�̊J���n�ɌK��A�����B�|�����L�ɑւ��āB�͂��͂��́A�V�̂����ł��Ċ撣���Ă����v
�@�搶�́A�˂̎��ォ����������A��������̎��ƂɎ��g��ł����邻�����B
�@��U�A���̔˒��֖߂�ƁA�������̑�����̓��䕽���������B���p�Ō�鉺�ɗ��āA�X�Ŏ��̋A���̉\�����̂��������B
�قǂȂ��A���c��Q�����}������A��ꂽ�Ƃ̘A�����������B���˒��Ƃ͊O�x������Ő^�����́A���x�[�ɂ����Q���̂����~��K�˂��B
��Q���́A�u��A��A��B���A��A���A��v�ƌ����ĉ�����o��ꂽ�B
�A�����x�ꂽ���Ƃ����l�т��āA�o�߂�����B
�@��Q���̂��b�ł́A�y�n��l���W�̏��ނ̈��n�����ߓ����ɏI���A���������\�����ő�Ꝅ�̌�n����V�J�n�̎����������s���Ƃ̂��ƁB���܂��A���R�˂̔ˎD�ƐV�����̌����䗦��������Ȃ����ƂɋC��a��ł���ꂽ�B���{���������ɂ́A���ݒ��̐V�J�n�����Ď��������ق��Ȃ��悤���B�˂̎��Ԃ���g�ɔw�����Ă�����B
�@���ɂ��b�����邱�Ƃ����邪�A�O�ŕ��������}���̎҂��҂��Ă���B�b��������ɂ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�����y�Y
�@�����ɒ��������ɂ͖�ɂȂ����B
�Ȃ►�����A���������������A�����������҂��Ă����B�䕚�i������␅�����s����ȂNjߏ��̕����W�܂��Ă���ꂽ�B
�@�Ƃɓ���O�ɁA�[�֏����`���B���������ɂ���ԂɁA�̍�Ə�����������B���̖�����ɁA�ǂ̎������яオ��B�J�^�J�i��Ђ炪�ȁB�傫�������ꂽ���������ǂ��ǂ����B���O�N�͊撣���Ă���ȁB
���������A�����������ŕ|�����Ɏ�������B�T�Ɋ���ĕ����ƁA�u�����v�Ƌ������B�F������B
�u��������ł���I�@��������ł���I�v
�Ȃ͉��x���������B
�}���ɗ��Ă�������������ߏ��̕��Ɏ���U�镑���A�����т����������o�����B�ЂƂ�����b���e�݁A�����̔���Y�ꂽ�B
�������A��т�����̕��̗l�q���C�ɂȂ�B���̌��ǂ��āA���̕����֍s�����B
���́A���O�̕a����ڂ����������B
�u�ŐV�̈�w�ł����߂��v
���͎₵���Ԃ₢���܂܁A����グ�Ȃ������B
�@���ł́A�[�֏����W��ɂȂ��Ă���B���̓��̖�A�g�����c�l�ȂǑ��̎傾�����҂��W�����B
�������܂��A���̊F����ɂ��l�т�\���グ�Ȃ���E�E�E�B
���N�̉āA�}�ɑ����o������A���N�]��������J�����̂��B���̊ԁA�a�l�����l�����������Ƃ��낤�B���Ò��ŁA�C�ɂȂ銳�҂��������B�����A�A��̍⓹�����������Ă��ꂽ�쑾�Y�N�̖�����́A���̓~������Ȃ������������B���̑呛���̎��ɉ���l���������悤���B���l�͉�������Ȃ����A�����A���f���|�����ɈႢ�Ȃ��B
�u��搶�A�����͂ǂ��ł����B�ِl�����悤�悢��b�ł����H�v
�u�������͌�s���ł�������Ⴂ�܂����H�v
�u�V���l�̂��Z�܂��́H�v
�@���̎҂����X�Ǝ��₷��B
�@�����A��������@�g�́w�w��̂��T�߁x�A�w���������V���x�A�w�����G�}�x���̑��A���낢��ȏ��Ђ�ŐV�̈�Ê��Ȃǂ��������B�F�͎�ɂƂ��Ē����������B
�@�����̋������ŐÂ��ɓ��������V����ǂ�ł������O�N���A
�u���̑O�̒n�k�B�l�c�������ꂽ�I�v
�u�����E�E�E�[���A�S�[�Ɩ��Đ����A�h�ꂽ�v
�u���]�L�̓V�ЁB���Ҏl�S��\���l�A�����l���S��\��l�A���ꂽ�Ǝl��ܕS���\�܌��A�������ꂽ�Ɣ���O�S�Z�\�܌��Ƃ���܂���v
�u�ǂ��H�@�ǂ��H�v
�u�����ɏ����Ă���܂��v
�u�Ӂ[��v
�@�V���Ƃ́A�����������̂��Ƃ��������͋C�B
�u���O�N�͂����ȁB���炷��Ɠǂ߂āv
�@�����A�������Ƃ���A
�u���ꂩ��́A�N�����ǂ߂�悤�ɂȂ�܂���v
�@�q�ǂ��B�͌[�֏��Ŋw��ł���B�ǂ߂Ȃ��͎̂����B�����ɂȂ��Ă��܂��B�F�������Ɏ����A���������Ȃ���������B
�@�b�́A�������֔�сA�������֔�сA��X���܂ő������B
�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W���@�@�@�@�@�@�@�ڎ��֖߂�
�����Q�l��
�@�E�Q�l�j��
�@�@�@�@�@�R�����E�Ғ��u��J�N�I�搶���ˏW�v�E�E�E�E�����ܔN�Z������C�t�̍�J�N�I�����c�x���ق����̏���
�@�@�@�@�@�@�w�E�E�E(�����́j�s���n�N(���j��B�����a�C�j�t�A�l�j�m�点�ʓ��p����A��Z�i�̕t�����j�K��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`���A���Ӊ��E�E�E�����̓�a�A��Y�̋�S�v�����A���ɒf����������B
�@�@�@�@�@�@�@�V�A�g�J�N�Y�i��J�N�I�j�@�L�A�l�m�~�q�x���̃j�����A�^�G�Y�A�R�}����E�E�E�x
�@�@�@�R�����E�Ғ��u�N�I�搶���������ȏW�v
�@�@�@�@�@���Y���u�ō��w���v�i��������}���ًߑ�f�W�^�����C�u�����[�j
�@�@�@�@�@�\���u���m�I�s�v�i�L�����j�E�ߐ������҇Y�j
�@�@�@�@�@�@�@�w�E�E�E�V�����m���i���n���j�J���m��叕�i���E�E�E�ؒ����T���t�����V�X�R�j���X���n����i���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�����V�����ꌩ�X���j�A�������L�V�E�E�E�x
�@�@�@�@�@�u����{�ËL�^�E�]�ؘk�����L�E���v������w�j���Ҏ[���E�E�E�E�����l�N�㌎��\����̓��L�i�����j�ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�w�E�E�E�����E�E�E�錾���A����A�`�M�@�V�ޔV�ِl���A�B�݉ƁA���Ɖ����A�ߗҔ��A���������A�����ݘZ�痢�O�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�������앐�c�E�c�ӁA�̌\��ƔV�A?�i�]�ؘk���j���V�a[�|]�A���Y�V��O�匾���A���Ɖ����A���m�w�A�X�X�Ɛ���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�̉͑��E���n�P��D�A�g�\��P��D�E�E�E�x�@�i[ ]�͊������Ȃ����߁A���ӂ̓��Ď��j
�@�@�@�@�@���������V���E�����ܔN�O���Z��(����j�t����\�Z���i���{�}���Z���^�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@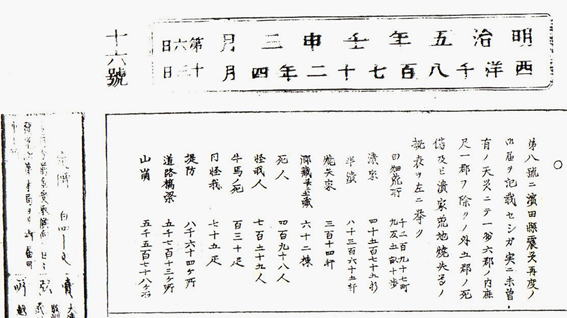
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�}���Z���^�[���s�́u���������V���v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�c�n�k�̎S���`���铌�������V���i�����j�E�E�E�E�EWikipedia�l�c�n�k
�@�@�@�@�@�u�����c�����j�v�i���R���j���l�j
�@�E�Q�l����
�@�@�@�@�@�C��@�b���u���R�˂̘ŗ����w�ҁ[���Y�搶�Ɓw�ō��w���x�v���R�w����G���E��Z�\�Z��(���a�O�N�j
�@�@�@�@�@�R�������u��J�N�I�̐��E�v���{�����o�Ŋ������
�@�@�@�@�@���䐳�v���u���㕟�R�Љ�o�ώj�v�������X�E�P�X�V�S�E�E�E�E��Z�͑���
�@�@�@�@�@�@�@�w�E�E�E���̑厸��(���D���́j�́E�E�E�������O�ȗ��@�܊p�L�\�Ȕˎm�𑽐��i���Ă����̂ɁA�V���{�̗v�H�ɎQ�����铹��
�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ���錋�ʂ��Y�̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�E�E�E�x
�@�E�o��l��
�@�@�@�@�@�����O�V�@�@�@�@Wikipedia�����O�V
�@�@�@�@�@���`���@�@�@�@Wikipedia���̋e
�@�E�Q�l�z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@���ߐV���E�E�E�E�E���ߐV����P�|�Q�O���i���J�ҁE����c��w�}���فj
�@�@�@�@�@���������V���E�E�E�E�EWikipedia���������V��
�@�@�@�@�@���{�ōŏ��̓S���E�E�E�E�EWikipedia���{�̓S���J��
�@�@�@�@�@����������������������������
�@�@�@�@�@�u���m����v�E�E�E�E�EDigital Gallery of Rare Books & Special Collections �f�W�^���œǂޕ���@�g�i�c���`�m��w�O�c���f�B�A�Z���^�[�j
�@�@�@�@�@���É���̋����́E�E�E�E�E���É���@�Љ�T�C�g
�@�@�@�@�@�唪�ԁE�E�E�E�EWikipedia�唪��
�@�@�@�@�@����E�E�E�E�EWikipedia�����₫
�@�@�@�@�@�V�[�{���g�E�E�E�E�EWikipedia���q�B���b�v�E�t�����c�E�t�H���E�V�[�{���g
�@�@�@�@�@���c���E�E�E�E�EWikipedia���c��
�@�@�@�@�@�u�����E�E�E�E�EWikipedia�u����
�@�@�@�@�@�������E�E�E�E�EWikipedia������
�@�E����ƂȂ����ꏊ�̍���

�@�@�ۂ̉Y
�@�@�@�@�@�@�@�@��铕