�����Q�l��
�@�E�Q�l�j��
�@�@�@�@�@�u�،ˍF����L�E���E��O�v������w�o�ʼn�
�@�@�@�@�@�u�،ˍF���E�Z�v������w�o�ʼn�
�@�@�@�@�@�u��c�x���j���E�����v�i�L�����Y�ق����u�������n���[�֎v�z�Ƃ̌����E�����ҁv�k���Ёj
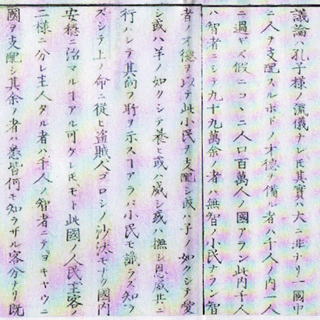
�@�u�E�c���Y���₵���@���{�̏h��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂩ��
�@�I��
�@�@�@�@��ŋ�
�@�ȏ�́A���A�E�c���Y�����ځA���A�����A�̌��������Ƃ�Ԃ������̂ł��B
���A�������ƂȂ��āA���̐��Ƃ��ŋC�y�ɉ߂����Ă��܂��B
���ɂȂ�ƕ֗��Ȃ��ƂɁA�������������ʂ��ł��B
���̌�A�،��F���t���̓��L�⏑�Ȃ��c����Ă��邱�Ƃ�m��܂����B���l�̓��L�⏑�Ȃ������o���Ȃǎ������Ƃ͑����܂����A�����������������ĊF�l�Ɍ䗗�ɓ��ꂽ���Ǝv���܂��B
�@�،ˍF��́A�����Z�N�\�ꌎ��\���̓��L�ɁA
�u�@�ɓ����������̂ɂ��Ď��̍l����q�˂��E�E�E
���B�̐��{�͂��̌`�͔���ł����A�䂪���ɔ�ׂĐl�q���i�i�ɗD��Ă���B������䂪���֎������ނ͓̂���E�E�E
��@���Ȃ�n���̊�����I������ƁA��������镾�Q������B
��@���{�̌����̑�@�́w�f�X�|�`�b�N�x�ɁB�����łȂ��ẮA����čs���Ȃ��B���ɋ���ƕ����́w�f�X�|�`�b�N�x�łȂ���E�E�E�v
�@�w�f�X�|�`�b�N�x�Ƃ͉p��Łu�ꐧ�I�v�̈Ӗ��ł��B
�Ȃ��A���������p��̃J�^�J�i�ɂ����̂ł��傤���B�u�ꐧ�I�v�Ɠ��{��ŏ����̂ɋC���������̂ł��傤���B
����ɁA�������N�̒n������c����ƂȂ����O����̎�����\���B
���F���ˎm�ŁA��Ɏ��ꌧ�m���⋞�s�{�m���߂������O�Ɉ��Ă��،ˍF��̏��ȂɁA
�u�@�n������c�ɂ́A�}�炸�������c���ɂȂ�܂����B
�w���ŋ��x���܂������A�����ς݂܂����B
�痢�̓��͈������Ɛ\���܂��B�f�l�ǂ����ŏ�����y�C����}�s��Ԃɏ��A���r���@���Ƃ��������Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ͏��Ȃ�����܂����B����́A���̐l�̂��߁A�l���̂��ߕs�K�Ȃ����ł��B�v
�Ȃ�ƁA�w��ŋ��x�E�E�E��X�͖،ˍF��́w��ŋ��x�ɗx�炳�ꂽ�����̂��Ƃ������̂��B
�@���́w��ŋ��x�ŁA���I����Ɏ^���������ߓ�\��l�̂��������ȏオ�ˊ�ƐE�A�������͔p���̍ۂɍĔC���ꂸ�A�����I�ɖƐE�ɂȂ�܂����B
��X�����ڂ��������O�V�ɂ������܂����B
�����O�V�̏����ɖ���������A�u�����v�Ɓu�����v���������Ă���ƁA�^�Q�Ŏw�E���܂����B��X�̎w�E�͓��Ă��܂����B���̌�A�����O�V�͊w�҂���_���̖�����Njy����A���ɑς���Ȃ��Ȃ��āA�����\�l�N�ɁA���������̗��z������w�^����Ӂx�A�w���̐V�_�x�Ȃǂ̎������ŁA�̔��֎~�ɂ���Ɛ錾���܂����B
���̉����O�V�́A�������{�𗝘_�I�ɗi�삵�A��ɓ�����w�̑����ɂȂ�܂����B
�@�@�@�@���ʐ��k�m�z��
�@���̎��͂Ɛ\���܂��ƁA�B�E���d����Ɛ錾���܂������A�l�N��̖����\��N�ɁA�܂����䖝���ł��Ȃ��Ȃ��āA����̑����J�݂��������܂����B
���̗v�|�́A
�u�ƂɗႦ��ƁA���Z�͎q��Ɉ�Ƃ̓�V��m�点��ׂ����B��������A�q����撣��A���Z�������邾�낤�B�����������B�����́A���̓�V��V���ŘR�ꕷ�������ŖT�ς��Ă���B�����ɒm�点�A����Ɏ���A�����͍��̓�ǂ𗝉����A�����ɋ��͂��邾�낤�B�v
�@�悤�₭������\��N�ɑ���{�鍑���@�����z����A���N�ɑ���̏O�c�@���I�����s���A����J����܂����B
�������A���̑I���͂Ƃ����ƁA�L���҂͍��ŏ\�܉~�ȏ��[�߂�j�q�Ɍ�����̂ł����B����́A�l���̂킸����p�[�Z���g���x�ł��B�[�֏����n�߂ē�\�N�߂��A���w�Z���n�߂ď\�ܔN���o���A�����̐l������������悤�ɂȂ����̂ɁA�����ꕔ�̐l�����I�����ł��܂���B����ȑI���őI�ꂽ����A�ʂ����č����̑�\�ƌ�����ł��傤���B
���̑��I���ɁA���ɑ���O�c�@�c���߂��c�䕽�A���ߍ�c�x������A���ɗ��������߂��܂����B
��c�x������ɁA���͕Ԏ��������܂����B
�u�E�E�E���̐����Ƃ́A������@���Ɍ������݁A�x�����������������A�w���僒���e���j�˗��V�@���R�����e���R�����V�x�A�}�h��g��Ő����ɖ�������E�E�E���́w����{���Ɨ�����m�ꖯ�x�A�Ȃ�Ŏ����A�ނ�w���ʐ��k�m�z��x�ɂȂ�悤���E�E�E�v
�����ς�Ǝ��ނ��܂����B
����s�����̋c��͂ǂ����B
����c�����������A�����\��N�Ɍ���c���̑I�����n�܂�܂����B������������A�L���҂͒n�d�܉~�ȏ��[�߂�j�q�Ɍ����܂����B���̌�A�����̒���c���̑I�����n�܂�܂����A�����悤�ɏ���������܂����B
���̂悤�Ȕ[�ŏ����͑吳��������̈���ܔN�ɓP�p����܂����A�L���҂͒j�q�Ɍ����܂����B�������̑�c�l�̑I���⎄���\�z�������c�����\�ɂ́A�[�ŏ����Ȃǂ���܂���B�������I�����ł��܂����B
���́A�������I�����ł��镁�ʑI���ɂȂ�܂����B����ɐ�����F����́A���a��\�N�̔s��œ��{�̐����͈�]�A�ς�����Ƃ��v���ł��傤�B���R�Ŗ���I�Ȑ����ɂȂ����ƁE�E�E�B
�@�������A�����_�̏ォ�猩��ƁA���܂�ς�����Ƃ͎v���܂���B�u���R�v�̐���ƕ��C�̈Ⴂ�͂��邪�A���C���̐����Ƃ����_�ł͓����ł��B�����͓���B���h�ȕ���M�S�ȕ��ɔC����B�����Ė��S�A�˗��S�E�E�E�����ƔC���A��l�C���̑̎��͂��̂܂܂ł��B
�@�@�@�@�J���t�H���j�A�B�̏Z�����[
�@�n����T���A���C���̐����ɂȂ�Ȃ��悤�A�₦���H�v���Ă��鍑������܂��B
�Ⴆ�A�ېV�̍��ɁA����@�g�搶������O�V�搶�ɖ��������̗��z�̍��Ə̂���ꂽ�A�����J���O���B�����āA���w�����\���N�������A���C���I���ċA��������A���̎��ۂ̂Ƃ�����̂��y���݂ɂ��Ă����A�����J���O���̏B�̂ЂƂA�J���t�H���j�A�B�ł��B
�ނ�͍����A�Z�����[�𑽗p���܂��B
�ʏ�̂��Ƃ͍s������c���ɔC���܂����A�d�v�ȈČ��́A���ځA�Z�����[�Ō��߂܂��B�ŋ߂̎���Ƃ��ẮA��Z��Z�N�̒��ԑI���ɕ����āA�����̈Č��ɂ��ďZ�����[���s���܂����B
�B�̒i�K�ŁA���̂悤�ȈĂɂ��Ď^���������A�^�ۂ�₢�܂����B
�쐶�����ی�̂��ߐV�ł̑n�݁A���Ɨ����T�D�T���ȉ��ɂȂ�܂ʼn������ʃK�X�r�o�K�����ꎞ���~�A���@�I����̕ύX�A���莑������B���ؓ����֎~�ȂǁA�\�Č����Z�����[�Ō��߂܂����B
�����ɁA���B�̌S��s�E���E��̒i�K�ŏZ�����[���s���܂��B���钬�ł́A���h�{�݂��[�����邽�ߑ��ł��邱�ƂɎ^�����������Z�����[�Ɋ|���܂����B�܂������ɁA�w�Z�o�c���s���w�Z�悪�A���t�����̂��ߑ��ł��邱�ƂɎ^���������A���邢�͊w�Z�̉��z�̂��ߎ؋����邱�ƂɎ^�����������Z�����[�Ɋ|���܂����B
���̑哝�̑I���̐܂ɂ��A�����̈Č����Z�����[�ɕt�����ł��傤�B
�I�����ڂ́A��c���̑I���ƍ��킹��Ɠ�\�A�O�\�ɂȂ�܂��B����Ȃɑ����̂��Ƃ���ʂ̎҂ɔ��f�ł���̂��A�^��Ɏv����ł��傤�B����ł����ɁA�ނ�͂���Ă��܂��B���ۂ̂Ƃ���A���[���́A�R���A��������܂����B�����Ȃ��ƌ����Ă��A�����l�A���\���l�Ō��߂�̂ł��B�^�ۂ���������c�Ăɂ͊S�����܂�A���R�Ǝv����c�Ă͂���Ȃ茈�܂��A���͋C�ɗ����������ȋc�Ăɂ͔��Έӌ����o�āA�펯����Ƃ���ɗ������������ł��B
�����Ȃ�ƁA���[�����l�͂��Ƃ��A���[���Ȃ��l���A���͂��ɕs���͌����܂���B�Q���̋@���^����ꂽ�̂ł�����E�E�E�B
�Z�����[�̑����́A�Z�����c�ł��B�c�Ă𗝉����Ă����Ȃ��ƁA�^�����Ă��炦�܂���B�c�Ă͊Ȍ��ɂ��܂��B�����āA�c�Ă�ʂ����Ɗ����ɉ^����W�J���܂��B���ߏ��̑��̍��^�������A�ŐV�̃��f�B�A�̊��p�܂Ő���͂���܂���B��t�ƃ{�����e�B�A�ł��B
�������������ɎQ�����A��Ă��ꂽ���ɂ͎����Ȃ�̈ӌ��������A�x�d�r�A�m�n���͂����茾�����Ƃ����������l�Ƃ��Ă̓��R�̎p�Ǝv���Ă��܂��B���ꂪ�����Ȃ��l�́A��̐��̂Ȃ��]���I�Ȑl�ƌ���܂��B�����āA�l�C���ɂ��Ă��āA�C�t�������ɂ͑�ςȂ��ƂɂȂ������X�̎��s����A�Q�����邱�Ƃ͓��R�̌����ł���A�`���ł���ƍl���Ă��܂��B
�u������Ƃ́A���̂悤�Ȏ҂ɂ͕�����܂���v�ƌ����U���Ĕ��f������A�u�����Ă���Ȃ����番��Ȃ��v�ƕs���������B�����āA�Z�����[�͓��{�ł͖����A�����ɗ�����ĊԈ�������f������A���{�ɂ͌����Ȃ��A���������Ⴄ�ƌ����B
�،ˍF��������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����ˁE�E�E���B�͉䂪���ɔ�ׂĐl�q���i�i�ɗD��Ă���B���I�c�@���䂪���֎������ނ͓̂���B�I��������ƈ���ɕ镾�Q������B
���ꂩ��S���\�N�B����ɔM�S�Ɏ��g�݁A���琅���̍������ւ���{���A�������̈Ⴂ�ƌ����ĕЕt���Ă悢���̂ł��傤���B
�@�@�@�@�@���w�̋���
�Ȃ��A�u���C���̐����v�ɂȂ�̂ł��傤���B
���A�E�c���Y�́A���ɂ��Ďv���̂ł����A�����̈�[�́u���w�v�̋����ɂ���悤�Ɏv���܂��B�Ȃ��A�����犿�w���E�E�E�Ƃ��v���ł��傤���A���B�A���{�l�̂��̂̍l�����ɁA�u���w�v�̐��_�����������H���Ă��܂��B
�����A���w����J�N�I�搶��]�ؘk���搶����w�т܂����B�����ȂƂ��뎄���g�́A�I���A���w����E���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�Ƃ��낪����@�g�搶�́A���������N�̍��ɁA���w�̖����ɋC�t���A�����ς�Ɗ��w�ƌ��ʂ��ė��w���w��܂����B
���̊��w�̖����Ƃ͉����B
����@�g�搶�́A�w�w��̂��T�߁x�̒��ŁA����Ղ��A���̂悤�Ɍ����Ă����܂��B
�u���w�́A�w������ē���ς݁A������l�ƂȂ��č������߂邱�Ƃ�������B���̌��ʁA�Ⴆ�A�l���S���l�̍�������Ƃ��āA��l�̗D�G�Ȍ��҂��������߂鑤�ɗ��B�����Ďc���\�㖜�l�]��́A�Ђ����炨���̖��ɏ]�����ƂɂȂ�B���̂��߁A�命���̍����͍���J���邱�Ƃ��Ȃ��A�������C�T���Ȃ��B����ł́A�ꍑ�̓Ɨ���������B�v
����@�g�搶�̂��̘_�ɁA�u���w�҂���l�ɂȂ��ĉ����������v�Ɣ��������̂��A���̉����O�V�搶�ł����B�����������́A����搶���뜜���ꂽ�悤�ɁA��l�C���A�����ƔC���̐����ɂȂ�܂����B���̌��ʁA��O�͐푈�̐��i�������A���͑�؋����������A�Ɨ��̊�@�������Ă��܂��B
�����āA�Ȃ��������ƂɁA���́u���w�v�̈��K�Ɓu�I�����x�v���������܂��B
���I�@���̂��ƁH�@�֘A������H�@�Ƃ��v���ł��傤���E�E�E�I�����A�䏳�m�̂悤�ɁA���h�ȕ���I��Ő��������C�����鐧�x�ł��B�u���C���v�Ƃ����_�ł͓����ł��B���̂��߂ɁA�Z����l�ЂƂ肪������l���A�ӎv�\��������@���D���Ă��܂��B
�n�������͖����`�̌P���̏��@
���̓_�����́A�u���c�����\�v�̍\�z�����ۂɎv�Ă��܂����B
���l���m��Ȃ����ɋc��Ō��߂�ƁA���s�i�K�ō���܂��B�����̋��͂������܂���B�����Ƌ��ɂ���A�J���ꂽ�c���ڎw���܂����B���̂��߁A�[�֏��Ɠ���~�n�ɂ���c�����̌��ւɕz���⌈�c���f�����A�w���k���V�e�@��X�ËL�Z�V���@�K�Y������j���T�Z�x�邱�Ƃɂ��܂����B�g����ޒ�����̌�B��h���A��R��₢�A���m�̓O���}��E�E�E�����ɂ��A�����ǂ߂Ȃ��A��������Z�p���Ȃ��A�����������{�݂��Ȃ�����ł��B�����ɍl��������@�ł����B
���̕��@�ɂ́A������̑_��������܂����B���̓s�x�A�e�Ǝq���b�������A�c��ʼn������ɂȂ��Ă��邩��m��A�e�q�Ƃ��ǂ��������w�Ԃ��Ƃ����҂��܂����B
�@�p�Ă�h�C�c�ȂǃQ���}�������ɂ́A�Z�������ڐ����ɎQ������Z������̓`��������܂��B�����̍��́A�ߑ�ɂȂ��đI���ɂ�邨�C���֖̕@��������܂������A�I���ɂ�鐭���̌��_�ɋC�t���A�����₤���߂��낢��H�v���Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A�c�Ă𑁂߂ɏZ���Ɍ��J������@��A�c��ŋc������O�ɏZ���̈ӌ����p�u���b�N�E�R�����g���A���邢�̓^�E���E�~�[�e�B���O�̊J�ÂȂǁB�Z�����炪���c����c�Ă���R����܂��B�����āA�d�v�Č��͏Z�����[�ɕt���܂��B�����̏Z�����c��Z�����[�́A�Z�����ꓰ�ɉ�Ȃ�����ǂ��A���ځA�����ɎQ������_�ŁA�Z������Ɠ������̂ƌ�����ł��傤�B�Ƃ��������ނ�́A�Z�����u��v�̊�{�ɗ����A�����ɏZ���̈ӌ��f���邩�A�����ĐM�������s����i�߂邩��₦�����S���Ă��܂��B
�@�����I���ɂ�鈾������c�l���x��̌����āA���̖��_�ɋC�t���܂����B�����Łw���c�����\�x�̍\�z�ł́A���ɂƂ��ďd�v�ȁw�i�O�m�厖���x�͋c��ŋc������O�ɑ����S�����W�߂ċc�Ă�������A�ӌ�������ΎO���ȓ��ɋߏ�̋c���\���o�āA�l���ڂɋc�����邱�Ƃɂ��܂����B
�@�Ƃ��낪���̓��{�́A�o�����̑I�����x��A�����āA�����`�͂�����������Ƃ��Ă��܂��B
�����ɂ́A�u�n�������͖����`�̌P���̏�v�Ƃ�����������܂��B
�����咣���A��͂Ō�Љ�����������V���ɂ�����܂����B�������N�l���\�O���́u�����v���E�E�E���̖��I�c�@�͌�ɂ��āA���������������Ŗ��I�̖�����n�߁A����ɖ��I�̌�����n�߂āA����Ȃ��X�����Ƃ������߂������獑�̖��I�c�@���J���悢�B
�n������c�Ő_�ސ쌧�ߒ����M�s�́A���I�̖���������Α��v���A���̂܂܉������Ȃ��Ȃ�A���\�N�o���Ă��l���͐i�����Ȃ��Ɣ������܂����B
����Ɠ����ł��B���{���A�n���̒i�K�ŁA�g�߂ȈČ��ɂ��ďZ���ɒ��ږ₢�����鐭�������������A���͂�T�ώ҂△�S�ł͍ς܂��ꂸ�A���������Ō��߂�����̂��̌�𒍎����A���͂┽�Ȃ�ӔC�̎p������������A����ɂ͍��̐����ɂ��Ă��ӔC�������ėՂލ����Q���̐������\�ɂȂ�ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�n������
���̕���@�g�搶�̏����ɁA�w�����_�x������܂��B
���̒��ŕ���搶�́A�����ɂ́u�����v�Ɓu�����v�̓�l������A�w�E�E�E�W���_���n�@���m�����W���j���U���o�@�����������T�Y�g�]�t���t�j�������e�@�u�����v���W���n�������@���_�A�@�u�����v�m�����i�����m�j�����}�f���@���F�R���������j�W���e�@����l�m�������S���j�{�V�@�e�n�m�����K���j���S�n���Y�@�V���V�e�^�������m�@�N�i���V�����g�~�X�����A���E�E�E�x
���̏����͖����\�N�ɏo�ł���܂����B�����l�N�̔p�˒u����A���{�͋��͂ɒ����W�����𐄂��i�߂܂����B����ɋC�t��������搶���A�������x����炳�ꂽ�̂ł��B
�������N�̒n������c���A�n���̈ӌ����ƌ����Ȃ���A���ǂ͌`�����̂��ƂɂȂ�܂����B���c�����ߖ����V���͂��߁A���I����Ƃ���A�����W�����ɂ�����Ȃ����߂⌠�߂����߂�����ꂽ�̂��F�������Ƃł����B�����Ă��̒����W�����̈É_�́A�����~�̓������������w���J�x�ƂȂ�A�u�X�J�v�ƂȂ�܂����B
�@�@�@�@�@����
����搶�̕��͎�@���ؗp����Ȃ�A�˂̎���Ɂu�����v�͓a�l�ɂ���܂������A�u�����v�͑��X�ɂ������ƌ�����ł��傤�B�N�v��[�߂Ă��A�˂͑��̂��Ƃ����܂��Ă���܂���B���̂��Ƃ͑��ŁE�E�E���l�̑��ݕ}���ő��̐��������Ȃ���Ȃ�܂���ł����B
���̕��������A���l�̏o���ŗ��w���w�Ԃ��Ƃ��ł����̂��A���ň�Â��m�ۂ��悤�Ƃ��鑺�l�����ݕ}���̐��_�������ł����B���������������A���l�𗠐邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��B
���l�����Ă��o���������[�֏����A���̎q�͑��ŋ��炵�悤�Ƃ����v��������������ł������Ƃł����B���ɐV���ȎY�Ƃ������������C����h�������u�{�\�`�K���v�������ł����B�����ɒx��܂��Ƒn�Ƃ������Д̔��̍ގЂ������ł����B���݂��ɕ����悤�ƏW�܂����������^���Q�������ł����B���������ʼn��Ƃ����悤�Ƃ����M���v��������������B���������B�́A���ӂ����f���鐭���̎����̂��߉���Y��Ċ撣��܂����B
�@�Ƃ��낪���������������s���Ɉς˂��A�s���͒����W�������āA���������{�ɗ���A���{�ɏ]�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����āA���̐��b��������������Ɏ��X�ƍ��̍s���������t�����A�����g�D�̖��[�ɑg�ݍ��܂�܂����B
�@���j�����ɖ߂����Ƃ͂ł��܂���B�������A�������E�E�E�������A���B�̂悤�Ȏ��H���n���Ɉ�����Ȃ�A���{�ɂ������Q���E�Z���Q���̐��������܂�A������Z�����ւ���[�������������t���������m��܂���B
���́A�_�̏�ʼn������v�������Ă��܂��B�S�z���Ă��܂��B
����̊F�l���A�ЂƍH�v���ӂ��H�v������邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڎ��֖߂�
�����Q�l��
�@�E�Q�l�j��
�@�@�@�@�@�u�،ˍF����L�E���E��O�v������w�o�ʼn�
�@�@�@�@�@�u�،ˍF���E�Z�v������w�o�ʼn�
�@�@�@�@�@�u��c�x���j���E�����v�i�L�����Y�ق����u�������n���[�֎v�z�Ƃ̌����E�����ҁv�k���Ёj
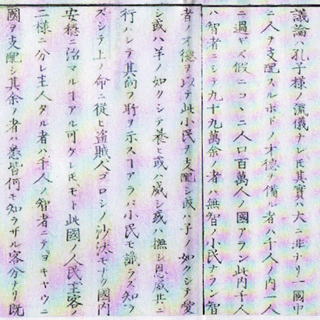
�@����@�g���u�w��m�X�R���v�O��
�@�@�u��g�Ɨ��V�e�ꍑ�Ɨ��X�����v�̈ꕔ�i�c���͕őւ��j
�@�@�O�s�ڂ���u��j�R�R�j�l���S�ݐl�m���A�����E�E�E�v�Ƃ���
�@�@�i�F�c��`�m���V�����Z���^�[�j
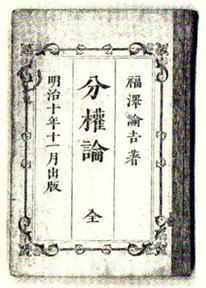
�@�@�@�@�@���V�@�g���u�����_�v�̕\���i�c��`�m�����Z���^�[�j
�@
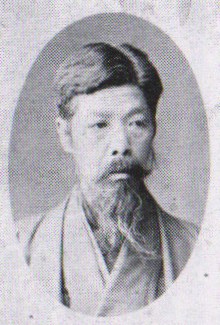
�@�@�E�c���Y�̎ʐ^
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�L���������j�����ّ��j
�@�@�@������\�l�N(�ꔪ���N�j�A���Y�\�Z�̍�
�@�@�@�u��t�E�E�c���Y�̎��R�����^���v�L���������j������
�@�@�@�@�@�@�@�u������N�x�t�̊��W�v�̍��q�����]��
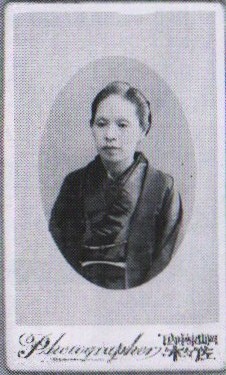
�@�@�E�c���Y�̍�
�@�@�@�@�E�c���q�i�c�M�j�̎ʐ^
�@�@�@�@�@�@�@�i�L���������j�����ّ��j
�@�@������\�l�N(�ꔪ���N�j�A���q�l�\�܍̍�
�@�@�u��t�E�E�c���Y�̎��R�����^���v�L���������j������
�@�@�@�@�@�@�@�u������N�x�t�̊��W�v�̍��q�����]��
�@�E���Q�l

�@�@�@�@�@����E�E�E�J���t�H���j�A�B�Q�O�P�O�N�P�P���Q�����ԑI��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�������[�҃K�C�h�i���{��Łj
�@�@�@�@�@�@�@�@���B�ɂ͓��{�l���������߁A���{��ł�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�������A���̊O����ł�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���̏B�ɂ��A�����̊O����ł�����܂����A���{��ł͏��Ȃ��悤�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���́u�������[�҃K�C�h�v���J���Ă݂Ă��������B
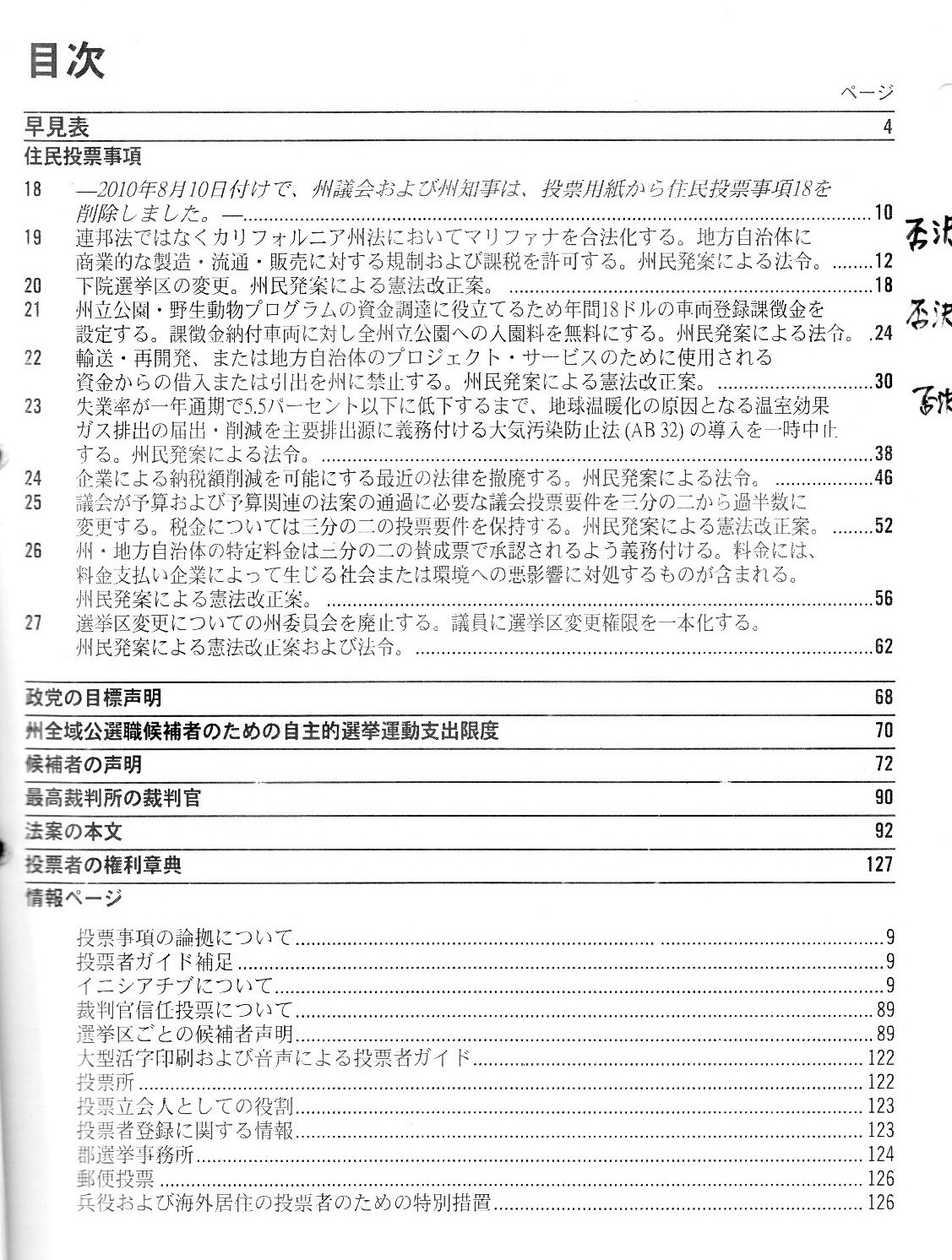
���̓��A��Q�P�̏Z�����[�������ɂƂ�A
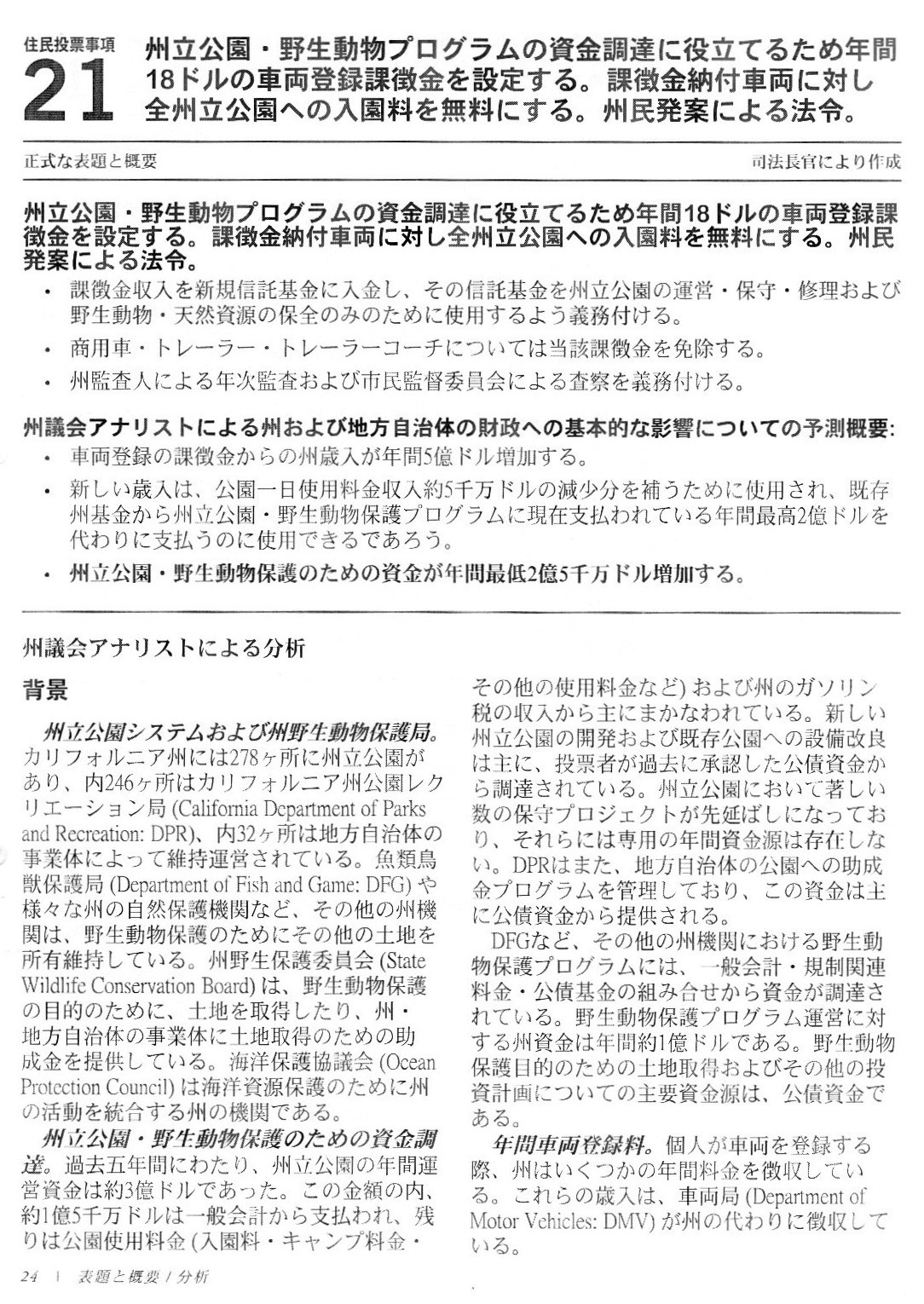
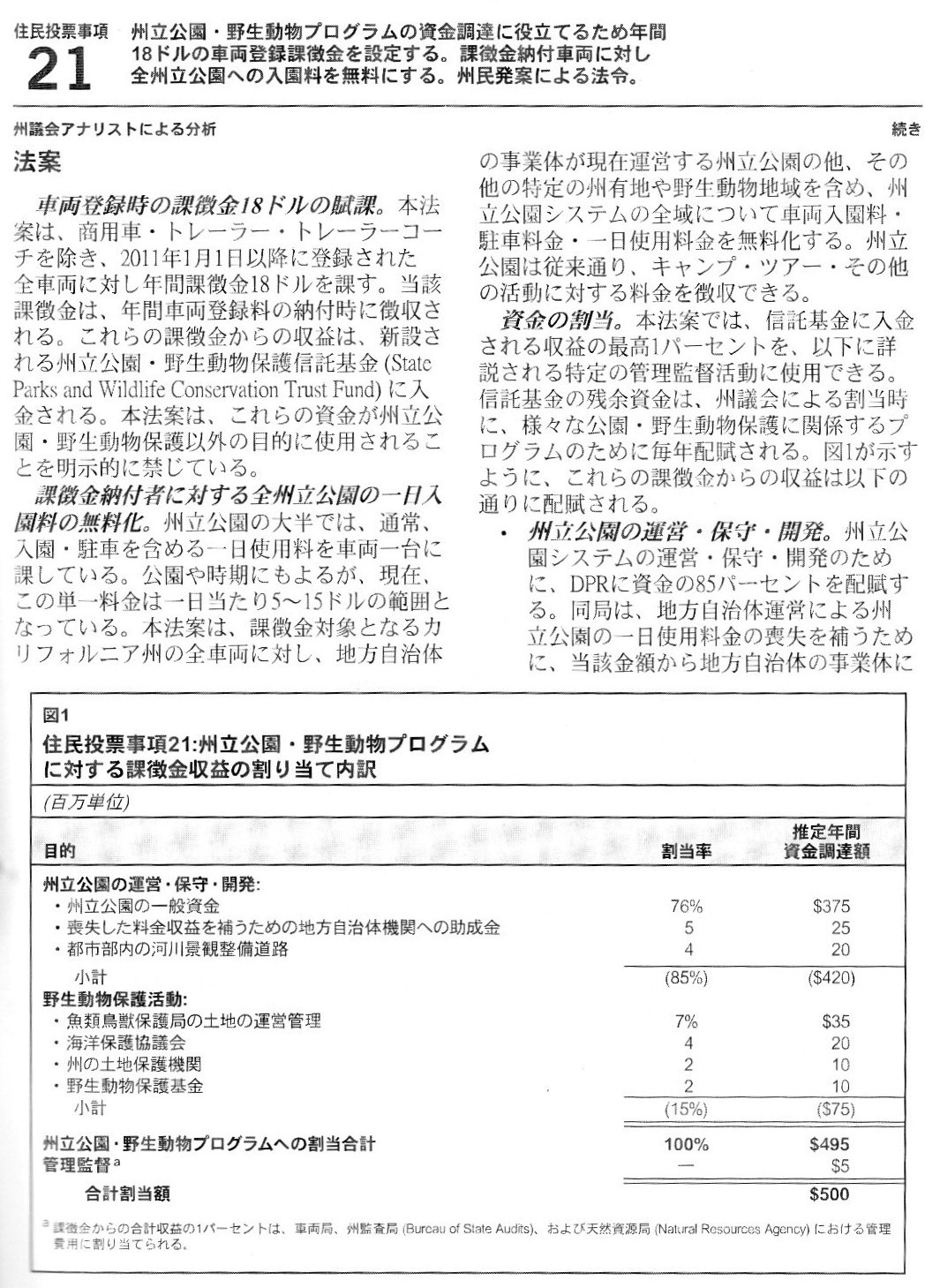

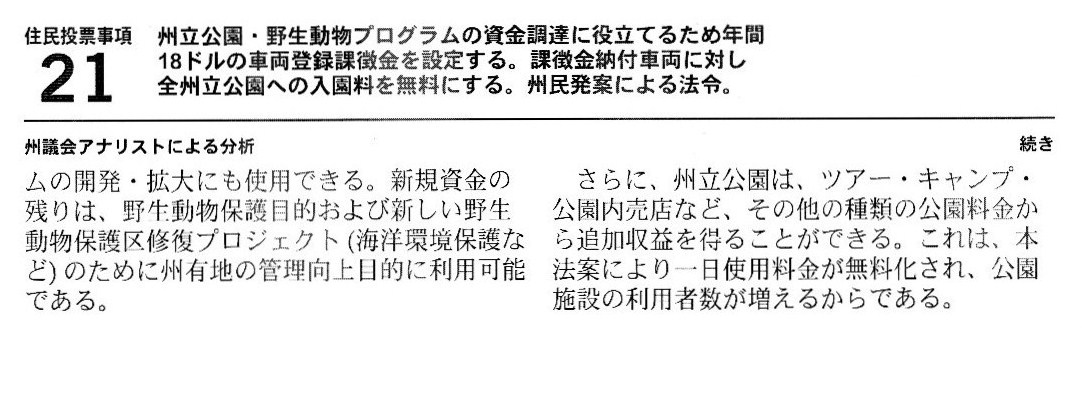
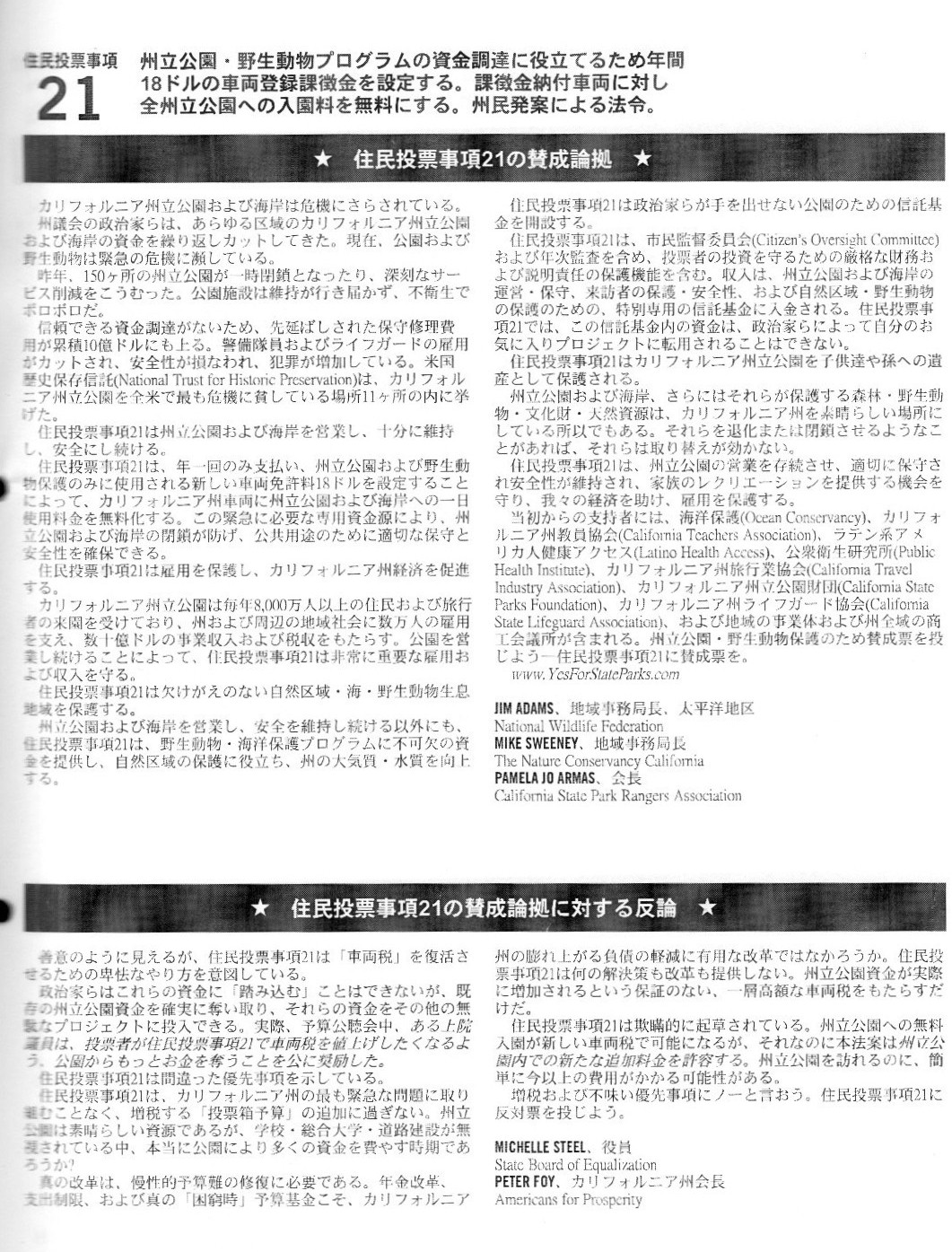
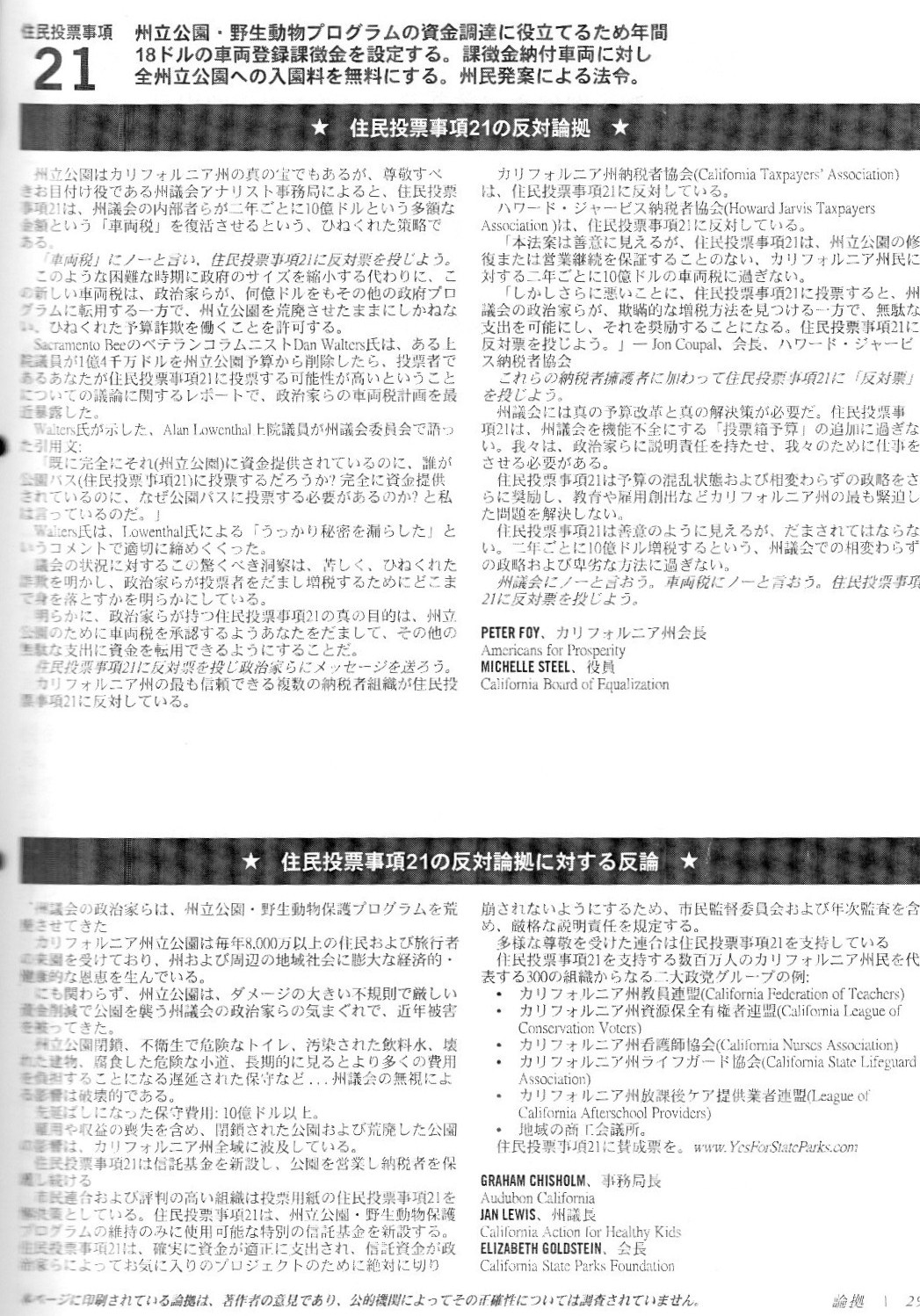
�J���t�H���j�A�B���I���i�Q�O�P�O�N�P�P���Q���Ηj���j�������[�҃K�C�h�i�B�������F��j�ɂ�����u�Z�����[�v
�@�@�Z�����[���ƂɁA�c�Đ����i�ړI�A���@�A���x�A���ʁj�ɑ���^���_�A���̔��_�A���Θ_�A���̔��_�Ȃǂ��ڂ�
�@�@��c���̑I���������ɍs���A�S�̂��P�Q�O�łƂ����c��Ȃ̂���
�@�@�e���тɗA�������
�@�@���ɃX�y�C����A�x�g�i����A�^�K���O��A������A�؍��ꂪ����
�@�@�i���{��ł��l�b�g�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B�V�J�S�s�͂P�Q������A���������{��ł͂Ȃ��j
�@�@�@�J���t�H���j�A�B�����g����[�S�i�p�V�t�B�b�N�O���u�s�E�y�j���X���w�Z��j�Z�����[�c�āEMonterey County Election
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����͑O��̒��ԑI���̂��̂ł��B���̑哝�̑I���ōX�V����܂��j
�@�E�Q�l�z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�����O�V�E�E�E�E�˓c�������u�����O�V�̓]���v�i�l�V�������ە�����w�I�v�j
�@�@�@�@�@�I�����x�E�E�E�E�EWikipedia���{�̑I��
�@�@�@�@�@�O�c�@���I���E�E�E�E�EWikipedia�O�c�@�c�����I��