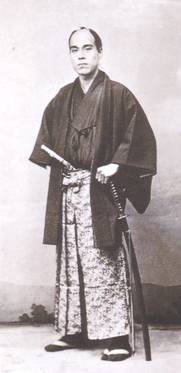
�@�V����1���~�D�����V�@�g����ɂȂ�܂����B
�@�Ȃ��A���V�@�g����Ȃ̂ł��傤���B
�@���V�@�g�͢�w��̂��T�߁v�̒��ҁB���̖`���̈�߁A
�@�u�V�͐l�̏�ɐl�炸�A�l�̉��ɐl�炸�v
�͗L���ł��B
�@���V�@�g�́A�V�ۂU�i�P�W�R�T�j�N�̐���ł��B
�@�����ېV(1868�N)�̂Ƃ��A���ɂR�R�B
�@���V�@�g�����������̂́A�]�ˎ���ł����B
�@���V�@�g�̕��́A���Ô˂̉������m�ł����B
�@�㋉���m�̖�����܂܂ɉ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ�
���̎p�����āA�������x�̖��������������Ă��܂����B
�@�(������)�唴���x�͐e�̓G�v(�������`�j�Ƃ܂Ō����Ă��܂��B
�@�����A�����ېV���B�����J�����B�V�������オ����̂��B
�@�m�_�H���̕����x�z�ɐ��܂����A�x�z�҂Ɉ˂肷���鐫�����̂ĂȂ���E�E�E�E�E
�@���̂��߂ɁA�N�����w����E�E�E�E�E���ꂪ�A�@�g�̢�w��v�ł����B
�@�������A�ېV��������̐����������炸�A���ɐ��{�Ɉ˂肷����A
���{�ցA���{�ւƂȂт��Ă���B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃł́A���������Ȃ��B
�@�@�@�@�u��g�Ɨ����Ĉꍑ�Ɨ����v�@(��w��̂��T�߁v�j
�{���ɂR�K
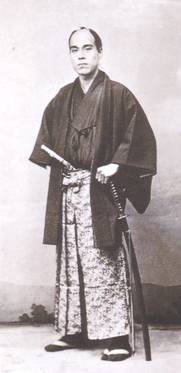
| �@�@�E�E�E�E�E�������A�����A�����Ƃ����s���ɗ���A���ɗ���A���邢�͖��S �@�@�C�Â������ɂ́A��800���~�A������l������700���~�̎؋������ɂȂ��Ă� �@�@�܂����B�E�E�E�E�E�E���V�@�g���A���Ȃ�����鏊�ȂȂ̂ł��B |
���V�@�g�́A�u�w��̂��T�ߣ�ɑ����āA����10�N��
�u�����_�v�Ƃ����{���o�ł��܂����B
���V�@�g�́A���������{�ɂ��W���̕��Q���w�E���A
�����̕K�v��������Ă��܂��B
[�����_�v���甲��(�����͌����A�ӂ�����ŏ����Y���܂����B)
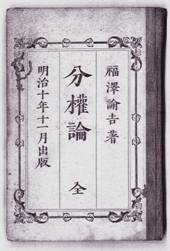
| �@�@�W���_���́E�E�E�E�E�n���ׁ̍X�Ƃ������Ƃ܂Œ����ɏW�߂āA �@����l�̎�����S���Ɏ{���A�e�n�������K���ɂ�������炸�A �@�^�������̔@���Ȃ炵�߂�Ɨ~����E�E�E�E |
�E�E�E�E�E�����܂��ɂ��̂悤�ɂȂ�A�S�������I�ŁA
���̓y�n�̓��F��ւ�͎����܂����B
| �@�@�������������W�����āA�n���̏����̐����̂��Ɓ������i�������j�܂� �@�����o���悤�ɂȂ�ƁA���̐��͂����▾�Ȃ�E�E�E�E �@���i�����Ǝ����j�̏W�����l���Ǘ��������A�E�E�E�E�E�Е��i�Ј��E���]�j���� |

| �@(�n���̎��������Ɂj��˒�(����l�j�̎��͊����i���{��l�j �@�̖��Ȃɂ��āA���̐g�������{�ז��̏���l���O�Ȃ炸�B �@�u�������i�Ƃ�Ȃ����Ɓj�����i��������j�v �@�@�@�@�i�������Ȃ����Ŏ����͔�ׂ�ƌ����ĈВ���R�E�����̂悤�Ɂj �@�����犯��(���{��l�j�̋C���������ď��O�̎ҋ��i���l�j�� �@����(�В���j�E�E�E�E |
���ɑ��k����A�u���⌧�ɑ��k������ƌ����E�E�E�E
�@�E�E�E�E�E�u���⌧�̎w���ł��B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B�v
���̐E�����A���̖�l�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
| �@�@�W���_�҂́E�E�E�E���{�́A�n�����l���i���j������(�n���������j�������� �@(��ׂ�)�D����(�����B�j�@�������{�������J���ŁA�n���̐l�������q�A �@�������_���ŁA�n�����ɖ��A�����͎����s���Ɋ���A�n���͖��ɏ]���Ɋ��� �@�i�Ƃ��悤�Ȃ��Ƃł́j������҂͂܂��܂������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�Ȃ�҂͂܂��܂��Z�ƂȂ�̂݁E�E�E�E �@�n���̐l���Ɍ��͂�������u�����̎�ɗ����i�����j��n���v���@���B �@����(���s�Ɂj����A���犵���̓���҂̈������̂݁E�E�E�E |
�� �� �� �S�S �� �~ |
������ �@�l�� ���@�� ����� ������ ���̑� |
| ���̑��̎��� | |
���� �@(���̎؋��j �@��34���~ |
|
| �n����t�� �@��P�U���~ |
|
| �� �� �� �o �� �S�V �� �~ |
�n���ւ� �⏕���� ��20���~ |
| ���̑��� �@�@�Ώo ��27���~ |
|
| ���̕ԍ� ������X���~ ������9���~ |
|
�@�@���̗\�Z
�@�@�@����17�N�x��ʉ�v
�@�@�@�@��82���~
�@�Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ώo
| ���� �@�@34���~ |
| �n����t�� �@�@��t�� �@�@68���~ ���� �@��t���� �@�@�@8���~ |
| ���⌧�� �@�⏕���� �@�@23���~ |
| ���S���g�p�� ���̑��P3���~ |
| ����(�؋��j �@24���~ |
| �� �� �s �� �o �� |
������C�U�� �@�@21���~ |
| �⏕���� �@�@22���~ |
|
| ���ʉ�v�J�o�� ���̑� �@18���~ |
|
| �ϗ��� �@�@7���~ |
|
| �����I�@�o�� | ���ݎ��Ɣ� �@21���~ |
| �`���I�o�� | �l���� �@�@�R�R���~ |
| �}���� �@10���~ |
|
| ���̕ԍ� �@���{26���~ �@�����@5���~ |
�k�L�����̗\�Z
�@�@�@����17�N�x��ʉ�v
�@�@�@�@�@162��8�疜�~
�Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ώo
�@�s�����́A���������⌧�̌�t����⏕���E���S���Ɉˑ����Ă��܂��B
�@�������悤�Ƃ���A���⌧�𗊂�Ƃ��Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E���V�@�g���뜜�������ˑ��̑̎��́A�����ς���Ă��Ȃ��̂ł��B
�@���̍\�������Ƃ����悤�Ƃ����̂��A�@�A�B�����̉��v���O�ʈ�̂̉��v�ł��B
�@�@�⏕�������A��t�����A��t�������B�����ڏ����E�E�E�E�E�����������Ϗ���
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�ł𑝂₷�ɂ́A�n��o�ς̊������������ւ�d�v�ɂȂ�܂��B
�@�������A���{�̉ߓx�ɕs�ύt�Ȍo�ύ\���́A�꒩��[�ɉ��P�ł������ɂ���܂���B
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�n��̌o�ϗ͂̊i���߂��t�����x�͕K�v�ł��B
�@�������A���s�̒n����t�Ō�t�����x�́A�����ւ�ȏɂ���܂��B
�@������x�A�O�y�[�W�̐}���������������B
�@���̍����͊�@�I�ɂ���܂��B
�@���N�A�ԍψȏ�̎؋����d�ˁA�ݐϊz�͖�800���~�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�@���̂悤�ȍ����ɂ��邽�߁A���́A�Ŏ������ł͌�t�Ō�t�������肸�A���ʉ�v�Ŏ؋����ĕ�U���A����ł���t�����s�����邽�߁A�s�������Վ���������i�{���ł́A5��6900���~�j�Ƃ����Վ��̎؋��ŕ���Ă���悤�ȏł��B
�@
�@�����n�����A���̂܂܂ł͑�ςȂ��ƂɂȂ�܂��B
�@�v�������s�����̉��v�ɔ����Ă��܂��B
�@�E�E�E�E�E�E���̂悤�Ȏ����A�{���ɂ��s�����v���i�{�����������A�s�������v���i�����ݒu����܂����B
����17�N6���@��1��@��ᒬ�c��
���@�k�L�����s�����v���i�{���ݒu���@����@�@�@�@�@��
���@�k�L�����s�����v�R�c��ݒu���@�@����@�@�@�@�@�@��
����17�N9���@��2��@��ᒬ�c��
���@�ꌈ�����ɂ��
�@�@�k�L�����ېݒu���̈ꕔ������������@����@�@��
�@�@�@�@�@�i�s�������v���i���̐ݒu�j
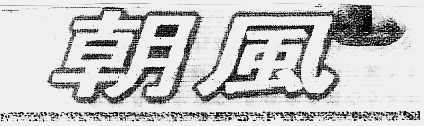
http://www12.ocn.ne.jp/~jiti2/
�@�@�n���������m�������
�@�@�@��\�@���@�{�@���@�M
�@�@��P�S���i�s�������v�j
�@�@�@�@�Q�O�O�T�E�P�O�E�U
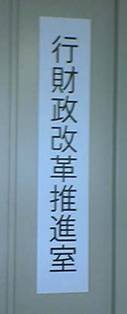
�푈�ւ̓����A�܂��ɂ���ł����B
���ɗ���A���ɏ]���A�Z�������ɍl���Ȃ��Ȃ�܂��B