�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����̂��T�߁v�i�v��Łj
�@�@�@�@�@�@��S��
��\�Z�́@�@�E�c���Y��̋�Y
�@�@�E�c���Y�̖��I�c�@�ݗ������_
�@�������N�̈ꌎ�ɁA�_�ޏ���ɂ��A���I�c�@�ݗ��̌����������{�ɒ�o����A�^�ۗ��_�ŕ����܂��B
�@�����ܔN�ɂ́A�����̏Z�ވ������ŁA���̑�c�l�̑I�������{�����E�c���Y�ł����A����c�@�̐ݗ��ɂ͎��������ƍl���܂��B�܂��܂��w�l���m�q�����_�J�P�Y�x�Ȃ̂ŁA���̔�p�̔���������ɉA�c��̔����Ŗ͔͂ƂȂ�l����\�����邱�Ƃ��Ă��܂��B
�@�@����y�W��_�m��
�@����c�@�̐ݗ��ɂ͎����������������E�c���Y�ł����A���c���ɂ́w���I�c�@�m�V�j�t�菑�x���o���āA�w���c�����\�m�c�āx�̕����Ō����̈ӌ����ė~�����Ɗ肢�o�܂��B
�@�܂��́w����y�W��_�m��x�A����̈ӌ����܂Ƃ߂Č��c���A���A����Ɛςݏグ�A���{�����W����n������c�Ɏ����グ��B�ނ�̓w�͂̌��ʁA����A���̉�c�͌����S��Ƃ͍s���Ȃ��������A�Վ�����ňӌ����܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�@���X�^�t���A���@
�@�w�L����c�����V�@���@���_�j���X�w�V�x�́A�w�O�m�����x���Ï�����悤�ɂȂ��Ă���̂ɁA�����̎��Ԃ́w�㉺�u��x�ƂȂ��Ă���B���̂��߁w���X�^�E���A���x�ƁA������Ȃ�Ɠ�\�Z�������Ă��܂��B���e�͉����肩�˂܂����A�Q�l�܂łɗ�L���܂��傤�B
�@�@�@�w�@���������j�l�w�e���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@��z�������X�^�E���A��
�@�@�@�@�@����@�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���Б��Ѓm�����X�^�E���A��
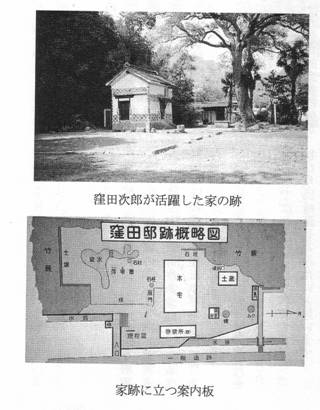
�@�@�@�@�@�d�ŏ��X�^�E���A��
�@�@�@�@�@��n�m���D���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���H�C�U���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���Ə��X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�䊯���������˒��m�s�X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�|�W���s���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�p�͎ŋ��{�s�q�������X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�����w�Z�����w�Z�m���E���ۏ��X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���w�����m�艿���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�w���w�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�����g���q�g�m����@���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�ٔ��ܔ����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�������ك[�Y�����m�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�㏑�l�m�����`�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���Ѓm�䐢�b���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�B�Y��Ў旧�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���c������㓏�m�V�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@���ȃw��掟�m�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�����ƃm�䌟�����X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�䊯���j�e�c���j�W���X�^�E���A��
�@�@�@�@�@�����m�E�����W�㓪���ȃe����������X�^�E���A���@�@�@�x
�@�����̋^����������߂ɁA���c���ɗՎ��c�@���J���K�v������ƌ��߂ɔ���܂��B
�@�@�����m��
�@��������́w���X�^�E���A���x�����钆�ŁA��Z���̉�c�Ŏ��グ��ꂽ�c��ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����܂����B
�@�w�����@�����m���x�E�E�E���̗v�|�́A�u����܂ő��̑���̋����́A���������S�A�܂薯��ŕ������B�Ƃ��낪�V���{���ł��āA�ːЎ�����x�@�A���H���h�̉��C�ȂǑ������˒��̎d���ɂȂ����B�d�Ő��x���ł��Őł͑S�Đ��{����������̂�����A�˒��̋�����A���{��������d���ɂ��Ă͐��{�A�܂芯��ŕ����ė~�����B�v�E�E�E�����ɒʂ�����ł��B���̎���́A����Ɩ���ɕ����܂����A�����ł͍��łƒn���ł̊W�ł��B�s���ɂ́A�Ǝ��̎d���̂ق��A���⌧����ϔC��ϑ����ꂽ�d��������܂��B���낢��Ȏ�ނ̕⏕���╉�S����������܂��B���ɕ��G�ɂȂ��āA���⌧�̎d�����A�s���̎d�����E�E�E�E�@�I�E�`���I�ɂ͋�ʂ���܂����A��ʂ̏Z���ɂ͋�ʂł��܂���B��l�Ɂu���Ƃ��Ȃ�Ȃ����v�Ɨv�]����A�u���⌧�̕⏕���Ƃł��������ł��v�Ɠ������A�s���̎d���̂͂����A���⌧�̎d���ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ȏ�c�_�ɂȂ炸�A�u��낵�����肢���܂��v�ƌ����ق��Ȃ��B���z��H�v��j�Q���Ă��܂��B�⏕�������邩���т��E�E�E���E�n���o���̍��������̗v���ɂȂ��Ă��܂��B���⌧�̎d�����A�s���̎d�����m�ɂ��āA���̌o��S�𖾂炩�ɂ���K�v������܂��B
�@�@�����ꑰ�m��
�@�w��O���@�����ꑰ�m�x�E�E�E���̗v�|�́A�u�܉ӏ��̌䐾���́w�����m蛏K���j���V�n�m�����j��N�w�V�x�̗��O�Ɋ�Â��A�����l�N�ɉ���߂��o���q����l�̖��̂��p�~�ɂȂ����̂�����A�ؑ���m���̖��̂��p�~���ׂ����B�����āA�ؑ��m���ɂ͓��ʂɊ���ȌY���Ȃ����邪�A������~�߂�ׂ����v�E�E�E�����̗ǎ��������Ęb�������A���݂��ɕ����荇���铖�R�ȋA���ł��B�b�������u���݁v���쒀����A�b������Ȃ���u���݁v���͂т���A�ƌ�����̂ł͂Ȃ����E�E�E�l�����d�������`���琶��܂��B
�@�@���m��
�@�w����@���m���x�E�E�E���̗v�|�́A�u�����ɕz���≺����Ȃ��肽���́A�������������d�łŏ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�S�����������̐ӔC�ŕ����悤�Ɂv�E�E�E�E�c���Y�́A���m�ł͂Ȃ������ɕ��R�˂̔˒��ږ�ɔC�����A�ˍ̐����ɋ�J�����o��������܂����B�}�ꂵ�̂��Ŏ؋����d�˂邤���ɁA�N�v�ɂ��x�����\�͂��A���͂�݂��Ă���鏤�l���Ȃ��A�ˎD�̑����ɗ����Ă��܂��A����ɂ͍��_�⍋���֖������������I�Ɋ���U��A�˂̐M�p�𗎂Ƃ��A�o�ς����������Ė��ˑ̐�����̌����ƂȂ�܂����B���̂悤�Ȃ��Ƃ��x�ƌJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��E�E�E����������ɒʂ�����ł��B�����E�Z�����m��Ȃ������ɖc��オ��A�N�Ԃ̐Ŏ��̏\�{�ȏ�����܂��Ă��܂��������ǂ�����̂��B�Ŏ��ɂ��x�����\�͂��Ă��葱��������͖����̔ˈȏ�Ɍ������A��ςȖ��ł��B�u���肢���܂��v�ƌ�������l����ƂɔC���A�����̏펯���ʂ��鐭���̎d�g�݂��Ȃ��������߂ƌ����ق�����܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���̐���
�@�@��p�����m�� �@�@�@�i��p�o���j
�@�w�攪���@��p�����m���x�E�E�E���̗v�|�́A�u���̖��́A���{���ƍ����ɂƂ��čő�̎������B������ɍ����ɉ���z���≺�₪�Ȃ��̂́A�܉ӏ��̂������́w�L�N��c�����V�@���@���_�j���X�x�V�x�ɔw���Ă���B�]���Ă��̐퓬�͓��{���ɊW�Ȃ��A����ɎQ�^���������݂̂̎����ɉ߂��Ȃ��B�]���Ă��̔�p�́A�呠�Ȃ��略�킸�A���̊����̎����ŕ����ׂ����v�E�E�E���̂悤�ȍl�����ɗ��Ȃ�A���{���푈�ւ̓�����ނ��Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B
�@�@���̑��̋c��Ƃ��̌�
�@�d�ŁA����A�����A���I�A�B�Y�Ȃǂɂ��Ă����グ���Ă��܂����A�Ō�ɂ�����B
�@�w��\�����@�ėA�o���m���x�E�E�E���̗v�|�́A�u�Ă̗A�o���ɂ��ẮA�Ẳ��i����Γ���l�~�ȉ��ɂȂ�ΗA�����A�Z�~�ȏ�ɂȂ�ΗA�o����B��������A��Ȃ��ƒn�̔_�����A�����Ȃ����Ƃ����ď��l�ɔ�����������鎖���Ȃ��Ȃ�v�E�E�E���̌�A�đ����Ȃǂ��N���܂����B�����ł́A�N�X�A�Ẳ��i���������ď������s���Ȕ_���ɂ͐g�ɂ܂����b�ł��B
�@���̊����͌E�c���Y�����[�h���A�n����t�A�m���A���t�ȂLjꕔ�̒m���w���Q���������̂ł��B�������A�����̐l�����̊����ɊS�������A���ɂ����̋c����l���A�T���l��O�ɓ��c���Č��c�������Ƃ́A�����Ƃ��Ă͎a�V�ŁA�����ɂ����Ă����P�����̂�����܂��B
�@����̋c��ł́A��]����ΒN�ł��Q���ł��܂����B���l���ǂ̒��x�Q���������肩�ł���܂��A�����̏��߂ɁA���̂悤�ȐV�������@���̗p���A�Z�����l����@��^����ꂽ���Ƃ͋����[�����̂�����܂��B�����āA����őI�o���ꂽ���̂����̋c���ɂȂ�܂��B���l�ɑ��őI�o���ꂽ�҂��A�Վ�����̋c���ɂȂ�܂��B��������T�����邱�Ƃ��ł��܂����B���c�����̂�������̏������̒��łǂ͈̔͂܂ʼn�c���J���ꂽ���s���ł����A�Վ�������̑��ƌE�c���Y���Z�ޑ�\����̌��c�͎c���Ă��܂��B
�@�����������Ō��c�����c�Ă��A�w�����ꑰ�m���x�A�w���m���x�A�w��p�����m���x�Ȃǂ́A����Ő�̂Ă��܂����B
�@�����̂قƂ�ǂ͎m���ł��B�����āA��p�����̖��́A�����A�傫�Ȑ������ɂȂ��Ă��܂����B���͐��{�̏o��@�ւɉ߂����A���{�C���̌��߂̂��ƂŁA�����̋c������グ���ɂ͍s���Ȃ������̂ł��傤�B
�@�̐S�̒n������c�́A������������p���̂��߉����ƂȂ�A�E�c���Y��̊����͓ڍ����Ă��܂��܂����B
�@�@��K�\���m�c�_
�@�c�_��i�߂�ߒ��ŁA��R������܂����B���̗Վ��c��͕s���K�Ȃ��̂ŁA�����̋c����撷�E�˒��������đg�D����܂����B���̂��߁A�����̐��͂����掂�\�����������悤�ł��B�c����I�ђ����čĉ�����ƌ��Ɏf���𗧂Ă܂������A����ɂ͋y�Ȃ��ƌ��͉��܂����B
�@�܂��A��c�����w���������̎҂ɂ��A�V������ɓ��e������܂����B�����̋c�ẮA���{���猈�c�����߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�������q�����Ă��邪�����̎���Ƃ�������Ă���Ƃ�����|�̂��̂ł����B�����ŌE�c���Y��́A�����ǂ̂悤�ɋc�_�������L���m���Ă��炨���ƁA���c��X�֕�m�V���ɓ��e���܂��B��\�������Ȃ钷���̌��c���A�������N�\���\�l������\�����ɂ����Čܓ��Ԃɘj���ĐV���Ɍf�ڂ���܂����B����Γ����̑S�����ł��B�傫�Ȕ������Ăт܂����B���ɂ͎^�ӂ�\����ӌ�������܂������A�c���̊e���ɂ��Ĕ��_������܂����B
�@������@��ɁA�E�c���Y��͒��Ԃ����Ċ^�Q�Ƃ��������c�̂�g�D���A�V������ɓ��e���邱�ƂŊ��H�����߂܂��B
�@�@�H�z�m���N���҃j�@�J�Y
�@���������N�ɂȂ��āA�Ăђn������c�̊J�Â��邹��A�c��Ƃ��āi��j���H�E���E��h�A�i��j�n���x�@�A�i�O�j�n������A�i�l�j�n���~���A�����Ēlj��Łi�܁j���w�Z�̐ݗ������グ���܂��B�������A�����͐V������Œm�炳���݂̂ŁA������͉��������ė��Ȃ��B�O�N�̂悤�ɗՎ��c����J���Č��߂��c��̈ӌ������Ƃ��Ȃ��A�T���l�̑I�C�ɂ��Ă����k���Ȃ����܂܁A�n������c�͊J�Â���܂��B���̂悤�Ȍ��̈����ɁA�^�Q�̒��Ԃ͕s���������܂��B���̏�A�n������c�ł͋c��́i�O�j�n������A�܂茧���ŋc����J���Ă��A�n�����i�{�m���⌧�߁j�̎^����\��A���ΎO�\��Ŕی�����܂��B�E�c���Y��͂��̂悤�Ȏ��Ԃ�ߊς��ĐV������ɓ��e���܂����A�n������c�̍Œ��̖������N�Z����\�����ɁA���{���V����������掗���z�����Č��_�̎������n�߁A�����ɓ��e�҂�V���̕ҏW�҂��E�����ꏈ������鎖�����N���܂����B�ނ�́A�V������ł̊����̓����f����A��ނȂ��B�E���d���邱�Ƃɂ��܂����B
��\���́@�@�w��̂��T��
�@�@����@�g�@
�@����@�g�͈ꖜ�~�D�ł��Ȃ��݁A�悭�m���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���̌��т������Ď]������̂��A���܂�m���Ă��܂���B�����ېV�̍��Ɋ�������@�g�̍����I�Ӌ`�͉����A���Ȃ�Ɍ����Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�@�u�����͐e�̓G�i�������j�v
�@����@�g�́A�ꔪ�O�ܔN�i�V�ۘZ�N�j�̐��܂�ł��B�ł�����A�������N�i�ꔪ�Z���N�j�ɂ͊��ɎO�\�O�B�l�ƂȂ�̐����ߒ��́A�قƂ�Ǎ]�ˎ���ɂ���܂����B
�@�@�g�̕��́A�L�O�i�啪���j���Ẩ����˂Ɏd���鉺�����m�ł����B�@�g�͕��̂��Ƃ����q�ɂ�鎩���u�������`�v�̒��ŁA�w�E�E�E���̐��U�A�l�\�ܔN�̑��ԁA�������x�ɑ�������ĉ������o�����A���s����ۂ�Ő������肽�邱���⊶�Ȃ�E�E�E���ׂ̈ɖ唴���x�͐e�̓G�Ō����E�E�E�x�Əq�ׂĂ��܂��B�@�g�̕��͊w��ɔM�S�Ȑl�ł������A������撣���Ă��A�������m�͂��܂ł����Ă��������m�ł��B���̖��O���v���A�u�����͐e�̓G�v�ƌ������̂ł����B
�@����@�g�͑��̎q�ǂ��Ɠ����悤�Ɋ��w�̏m�ɒʂ��A�_��Ȃǂ��w�т܂����B�������A�������x���x����w��ɖ����������A����ɗV�w���ė�����w�т܂��B�����đ��ɏo�āA�����^���̓H�X�֏m�Ŋw�т܂��B
�@���̕ӂ�̌o�܂́A�E�c���Y�Ƃ悭���Ă��܂��B���Y���A���߂͊��w�̏m�Ŋw�т܂������A��t�ɂȂ邽�ߏ����^���̖剺�̎t�ɂ��܂����B���Y�̏ꍇ�A��������ɍs���A��w���w��ł��܂��B���Y�͖����l�N����ܔN�ɂ����ē����ɑ؍݂��܂����B���̎��A�@�g�ɉ�������ǂ����s���ł����A�����ܔN���s�́u�w��̂��T�߁v���[�֏��̋��ȏ��Ɏg���A�V����G���ɍڂ�@�g�̘_���ɊS���Ă��܂����B
�@�@�u�u�C�̒Q�v
�@�@�g�́A�ېV��蔪�N�O�̈ꔪ�Z�Z�N�ɁA�A�����J�֓n��܂����B���̎��̑̌����u�������`�v�̒��ŁE�E�E�A�����J�̉ƒ�ɍs���ƁA���������ƂɁA�����֎q�ɍ����ċq�̉������āA��l�͂��̐��b�ő������Ă���B���{�Ƃ̓A�x�R�x�Ȏ������Ă���B�m������������ǂ�ŁA���Ă̂��Ƃ͒m���Ă�����肾�������A���̂悤�ȁw�Љ��̎��x�͖{�ɏ����ĂȂ��B�C�̊O����́A���䂢�Ƃ���Ɏ肪�͂��Ȃ��悤�ɁA���ۂɌ������Ȃ���Ή�����Ȃ��E�E�E�Əq�����Ă��܂��B
�@�����Ɏ��グ����̂́A�V�������Ƃ�Ȋw�I�Ȃ��Ƃł����B���Đl�ɂ��Ă݂�Γ��R�̂��Ƃ́A�킴�킴�{�ɏ����܂���B���̓_�́A��\�́u�����̎������@�A�����J�v�ł����b���܂����B���̃z�[���y�[�W�ŁA�^�E���~�[�e�B���O�̋c��͌���܂����A�^�E���~�[�e�B���O�̗l�q�͍ڂ�܂���B�����̂��Ƃ������ŁA�u�����Ƃ́A���玡�߂邱�Ɓv�Ɖ�����������ɂȂ�܂����A���ۂɂ��̒��ɏZ��ŁA�Z���Ɛ��������ɂ��Ď����̕K�v���������Ȃ���A���̐��_��������Ȃ��ł��傤�B���̂��Ƃ͑����������ł��B���������V���@�Ɂu�n�������̖{�|�v��搂��܂������A�����̎��ۂ������ł��Ȃ����߁A���Ɏ����Ēn�������������ł��Ȃ������ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�_�̎u�@
�@����@�g�́A�ĎO�ɂ킽���Đ��{�̖�l�ɂȂ�悤�A�U�����܂����A���̓s�x�A���ނ��܂����B�����ł��A�������͈��肵���E�Ƃ��Ċ�]�҂͑������A�Ƃ�킯�����͔p�˒u���ɂ���čs��������������ˎm�������A�����Ċ��E�ɏA�����Ƃ��܂����B�@�g���ˎm�̐Ռp���ł��B�������@�g�ɂ́A�l��������܂����B
�@�@�g�́u�������`�v�̒��ŁA�w�S���̐l���B���{�̈����ړI�ɂ��ĊO�ɗ��g�̓��Ȃ��Ǝv����ŋ���̂́A�L��i�Ђ����傤��������j���w����̗]���ŁA�����i������j�h�́u�_�̎u�v�Ƃ��ӂ��Ƃ���c�ȗ��̈�`�ɑ����ċ�����̖��ł���B�����̖�����܂��ĕ����Ɨ��̖{�`��m�点�₤�Ƃ���ɂ́A�V����l�ł��i�������j���^���̎�{�����������E�E�E�x�Əq�ׂĂ��܂��B
�@�����́u�_�̎u�v�Ƃ́A���g�o���̎u�̂��Ƃł��B���ɏA���A����ς݁A������~���ďo������E�E�E�E�q�Ɏn��̋����ł���A�ˎm���w���w�̋����ł��B�N���ނ�������E�ցA���{�ւƈ˂肷�����āA����Ɨ��̐��_�������ẮA�������ɂȂ�Ȃ��E�E�E���������Ԃɂ����Ĕ͂��������Ƃ����̂��A�@�g�̍l���ł����B
�@�E�c���Y�ɂ��A���E�ɏA���@�����܂������A���ނ��܂����B�ŏ��͓�\�܍̎��A�ˎ刢�����O�����a�C�ɂȂ��A�ˈ�̈���ɐ�������܂����B��x�ڂ́A�O�\�܍̎��A�˂̈�@����w�Z�̋����̖����܂����B�������A��������f���܂����B���Y�́A�������l�̐��b�ɂȂ��Ďn�߂��������̈�Ƃ��p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������܂����B�������A���ꂾ�������R�ł͂Ȃ������悤�ł��B���Y�͌�ɁA�䂪�q�����ցA��l�ɂ͂Ȃ�ȂƉ��߂Ă��܂��B����͂Ȃ����A���̑z���ł����E�E�E���Y�͖��ӂ����f���鐭����ڎw���܂������A��l�͖��O�̕����������A���{���i�̕�����������E�E�E��������܂܂ɂ��������Ȃ��A����ȑ������ꂽ����̖�l�ɂȂǂȂ�ȁA�Ƃ����̂����Y�̎v���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�w��̂��T�߁@
�@����@�g�ƌ����A�u�w��̂��T�߁v�E�E�E�Ƃ��낪�A���̖{�ŗ@�g�̌����Ƃ���Ƃ��낪�`����Ă��Ȃ��悤�ł��B�����悤�ɁA�`���̗L���Ȉ�߁w�l�̏�ɐl�����炸�A�l�̉��ɐl�����炸�x���A�@�g�̈Ӑ}�����悤�ɓ`����Ă��Ȃ��悤�ł��B�@�g�͉����������Ƃ����̂��A����܂ł��b�������Ƃ܂��Đ������܂��B
�@����܂Ŋw��ƌ����A���w�܂�ł����B�_���l���܌o�Ȃǂ��ËL���A���߂���B�����āA��߂����A����g�ɒ����A�ǂ��w���҂Ƃ��Đ������߂�E�E�E���̊w�₽�߂ɁA����Ȏ��ԂƘJ�͂��₵�܂����B���������ꂩ��̐V��������́A���������w��ł͐����čs���Ȃ��B����l���A�T�����A���f���A��������߂�u���w�v������B���̂��߂ɂ́A�����������Ȃ��Ă悢�B�N�������R�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł���B��������̂悤�ɁA���m�������w�ԁA�����Ď�ɐs�������߂Ɋw�Ԃ̂ł͂Ȃ��E�E�E�l�̏�ɐl�͂��Ȃ��E�E�E����l�����J�����߂́u�w��v�����߂��̂ł����B
�@�����ܔN�Ɂu�w��̂��T�߁v���҂����s����A�����Ɂu�w���v�����z����܂����B���̊w�����A��\�l�͂ŏЉ���悤�Ɏ���E�����̐��_�сA���w�����サ�Ă��܂��B�����āE�E�E�u�w��͕��m�������̂Ǝv���A�_�H���w���q�Ɏ����Ă͊w���x�O�����āA�w��ɂ��Ęb��ɂ����Ȃ��B���m�̒��Ɋw�������҂����邪�A�w��͍��Ƃׂ̈ɂ���̂��ƌ����A�����������čs�����߂̊�b�ɂȂ�Ǝv���Ă��Ȃ��B�����ɈÏ��o���邩�������A��_���q�����A���e�͍����̂悤�ł��A���H���Ď��ԂɑΏ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B����͋��ԈˑR�̈��K�ł���v�E�E�E�Əq�ׂāA���m�����łȂ��A�����S�ĂɊw�₪�K�v�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��B
�@���̊w���̍l���́A�@�g�Ɠ����ł��B�@�g�́u�w��̂��T�߁v�������I�ɔ���A���w�̋��ȏ��ɂ��Ȃ�܂����B�E�c���Y���A�����A�u�w��̂��T�߁v�����ȏ��Ɏg���Ă��܂��B���̂悤�ȓ����̏��猩�āA�u�w���v�́A�����ɕ���@�g�̉e�������̂ł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B
�@�Ƃ��낪�c�O�Ȃ��ƂɁA����@�g�̐^�ӂ͐�������������Ă��܂���B
�@�u�l�̏�ɐl�����炸�E�E�E�v�A�������A�l�Ԃ͕������A�Ǝv���͓̂��R�ł����A�����P�ɕ����������Ă���̂ł͂���܂���B�l�̏�ɐl�͂��Ȃ��̂�����A�ォ�疽������܂܂łȂ��A����E�����̐��_�������Ď���l���A���H���đO�i����悤�ɗ@�g�͌Ăт����Ă��܂��B
�@�u�w��̂��T�߁v�́A���̑薼�ɂƂ���āA����̏d�v�����������A���{�̋��琅���̌���ɍv�������Ǝv�������ł��B�����ē��{�̋���͐����A�m���Ώd�ōl����͂����L���͂��K�v�ȋ���ɌX���āA�q�ǂ������������ɋ�藧�ĂĂ��܂��B����������́A�@�g�̊��҂������̂ł͂���܂���B���̂悤�Ȏ�����w���d���́A���E�I�ɂ��̗��j�������ɓ��L�Ȍ��ۂł��B����@�g�́A�����������̏��߂ɂ��̖��ɋC�t���A�I�����E���čl����͂�{������𐄏����܂����B���������̌�́A��\�l�͂ł��b���܂����悤�ɁA��F�́u���璺��v�̂��Ƃŋ��炪�i�߂��܂����B���́A������������Ȃ��A�V���ɏo�������͂��ł����A�ȒP�Ɂw��c�`���̈�`�x��E�������A�l������Ȃǂ����Ȃ���A������͂��w�ԋ���Ȃǂ��낢��͍�����Ă���Ƃ���ł��B�Ƃ�킯�ߔN�́A�o�ς̕ǂɂԂ�������A���͂�����鎞��ƂȂ�A���ɍl����́A������͂�����̏d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�����̎�ɗ�����n���@
�@�@�g�́A�u�w��̂��T�߁v�̒��ŁA�u���̂���҂����߂�v�����̕��Q����̓I�ɔᔻ���Ă��܂��B
�@�u�E�E�E�ꍑ�̒��ŁA���������Đl�������߂�҂����l�A���̍����͂���ɏ]���E�E�E�����Ȃ�A���͕����Ɏ��܂邩������Ȃ����A�N���ނ������̂���l�ɗ���A����S�z���邱�Ƃ��Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�����Ƃ������ɖ��͍��ɗ���A�������Ȃ��E�E�E�v�B�l�̏�ɗ��ꕔ�̒q�҂ɂ�鐭���ł͍������Ȃ��B��l�ЂƂ肪�䂪�g�����߁A���ɗ��炸�A��g�Ɨ����Ă����A��������E�E�E�w��g�Ɨ����Ĉꍑ�Ɨ����x�E�E�E���ꂪ�A�@�g�̎咣�ł���A���ɏA�����A���ɍ݂��Ď�����H����@�g�̐M�O�ł����B
�@�����ė@�g�́A�����\�N�ɒ������u�����_�v�̒��ŁA���ɗ��钆���W���Ɛl���ɎQ���̋@���^���镪���������r���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�u�E�E�E�l���Ɏ�������^���邱�Ƃ͐S�z�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B�������A�w�l���Ɍ��͂�����͏����̎�ɗ�����n�����@���x�ŁA����ĉ��䂷�邩������Ȃ����A������������ɒ���Ĕ��Ȃ��邾�낤�E�E�E�l�̎��R�͂��̂悤�ɂ��Ĉ�B���͂܂��ɁA���̂��߂̕����̎����B�v
�@���R�▯���`�́A�̌����Ȃ���w�Ԃ��́B�����͖����`�̊w�Z�E�E�E���̍l�����́A�����̐i���X�̏펯�ł���A�E�c���Y���L���Z���Ɂw���n���K�m�����σ~�x�A�w�l�������m�[�����J�N�x���Ƃ��Ăт����܂����B�������A���́u�����͖����`�̊w�Z�v�Ƃ����l�����́A�������ē��{�ł͔F�����悤�ł��B�@
�@�w�����̎�ɗ�����n���x�E�E�E�����̏��߂ɁA�@�g�͂��̑�������̂ł����E�E�E�₦�����{�⌧����؋��̐���Ȃǎw�������͂��Ȃ̂ɁA�[���s�̂悤�Ȏs�����o�Ă��܂��܂����B�ˑR�Ƃ��ďZ���ɂ��`�F�b�N�@�\������Ă��܂���B�����̎d�g��������Ղ����āA�Z���̏펯���ʂ��鎩���@�\�������K�v������܂��B
�@�@�@�g�̕����_�@
�@�n�������̕K�v��������A���N�ɘj���Ę_�c����܂������A����@�g�̒����u�����_�v�����グ���Ȃ��͕̂s�v�c�ł��B�@�g�́u�����_�v�́A���̂܂܍����ɒʂ���̂ł����E�E�E
�@���̒��ŗ@�g�́A�����ɂ͐����Ǝ����̓�l������ƌ����܂��B�����Ƃ́A�O���A�����A�ݕ��ȂǑS����l�Ɋւ��錠�͂ŁA�����Ƃ́A�w�Z�A�q���A���H�Ȃǒn��̎���ɉ����āw���n���ɋ��Z����l���̍K����d�i�͂��j�邱�ƂȂ�x�Ɩ��m�ɋ�ʂ��܂��B�����āA�w�W���_�҂́E�E�E�������W��͌Łi���Ɓj��薳�_�A�����̍��ׂȂ���̂Ɏ���܂ł����F�i���������j����𒆉��ɏW�߂āA����l�̎�����S���Ɏ{���A�e�n�̋����K���ɂ��S�͂炸�A�V�����Đ^�������̔@���Ȃ炵�߂�Ɨ~����҂���B�x�E�E�E�S���e�n�������Y���̒��Â���E�E�E�@�g�̗\���̒ʂ�ɂȂ�܂����B
�@�����Ă���ɗ@�g�́A�w�����ɐ������W�����Ė�����Ɏ������W������Ƃ��́A���̐��͂���▾�Ȃ�E�E�E�̏W���͂����ɐl����������݂̂Ȃ炸�A���l�̏�K��ύX���l���Ǘ������߂ČX�ɏA�ĔV���Е�������̂Ȃ�E�E�E�x�@�܂��ɂ��̒ʂ�ŁA�����̌����܂ŏW�����āA�l�X���Ǘ������A���������āA�푈�ɒǂ����܂����B

�@�@����������
�@����ɗ@�g�́A�_�y���܂��B�u�W���_�҂͌����B�������{�̂݊J���I�ŁA�n���̏Z���͖��q�B�����͐_���ŁA�n���͊ɖ��B�����͎����s���Ɋ���A�n���͖��߂ɏ]���̂Ɋ����B�����Ȃ�ƁA�����钆���͂܂��܂������A�n���͂��܂Ōo���Ă��i�����Ȃ��B�v�E�E�E�n���͍l���悤�Ƃ��Ȃ��Œ����Ɏf���𗧂āA�H�v�����悤�Ƃ��Ȃ��ŕ⏕���ɗ���B�@�g���S�z�����ʂ�ɂȂ�܂����B
�@�����ė@�g�́A�u���̋撷��˒����A���{�̒n�����̕@�������������A����������Α����܂ŏo�}���A�擱���ĊF��Â߂�̂��d���B�����Ċ������A������́w���������啁i���Ȃ����̂�������j�x�E�E�E��ׂ邩�璹�̒��Ԃ��ƈВ����啂̂悤�ɁA�撷��˒��������C���ŊF���w�}���A�菑�̎���p���ȂǍׂ��ɒ��������A���x�������^����B����́A�W���ƌ��킴��Ȃ��B�v
�@�������N�ɂ́A�E�c���Y�炪�c�_�����悤�ɁA���{�����̎d���Ƒ������̎d������ʂ��A���{�����̎d���͊���A�������̎d���͖���Ƌ�ʂ��čl���܂����B�������N�ɏ��߂Č��߂��W�߂Ēn������c���J�Â��܂����B���߂͐��{�̔C���ł������A�����̐��Ɏ����X���悤�Ƃ��錧�߂▯��i�c��j�̐ݒu�Ɏ^���̌��߂����܂����B�Ƃ��낪���{���n�������̂��ߑS���ɑ�揬�搧�������A�撷��˒���C�����āA�ːЁA�����A�[�ŁA�x�@�A�w���ȂNJ��̎d�����`���t���A����ɐ��{�̖��[�g�D�����܂����B���̂悤�ȏ�Q���A�@�g�͖����\�N�Ɂu�����_�v���������߁A�x�������̂��Ǝv���܂��B�������A���͂ł��b����悤�ɁA���{�͒n����̐����ɑg�ݍ��ݒ����W�����ɓ˂��i�݂܂����B
�@�����A�����̐E�����u���������啁v�ɂȂ��Ă͂��Ȃ����E�E�E���̎w���ł�����B���̐��x�ł�����B���̕⏕���Ȃ��̂ŁE�E�E���⌧�̈Ќ���w�����Ă͂��Ȃ����B�߁i���݂����j�𒅂ďZ���ɐڂ��Ă��Ȃ����B�Z���̖����ɂȂ��Ă���ƏZ���Ɋ����Ă��������Ă��邾�낤���B
��\���́@�@���̎��R������
�@�@
�@�@�@�g�Ǝ��Y
�@�����悤�ȍl����������@�g�ƌE�c���Y�ɐړ_������܂��B
�@�E�c���Y�͖����ܔN����Z�N�ɂ����ē����ɑ؍݂��܂����B���̊ԁA���Y���@�g��q�˂����ǂ����A�肩�ł���܂���B
�@���傤�ǂ��̍��̖����ܔN�Ɂu�w��̂��T�߁v�̏��҂����s����A�傫�Ȕ������Ăт܂��B���̏��҂̒[���ɁA�@�g�̌̋����ÂɊw�Z���J�����̂ŏ��������A��������������L�����p���Ă͂ǂ����Ɗ��߂�ꂽ�̂ŏo�ł����ƋL����Ă��܂��B�����ǂ��Y�́A���{���傫�ڂ̖{�Ɉ�����Č[�֏��̋��ȏ��Ɏg���܂����B�����m�����@�g�́A���쌠�N�Q�ƃJ���J���ɓ{��A�@��Ɏ������݂��˂Ȃ��l�q�B���傤�njc���`�m�ɕ��R�o�g�̎҂����ĘA�����A���̊w���ے����R�V�\�Y���@�g�ɖʉ�ĎӍ߂��܂����B�����ċ㌎�ɂȂ��Ă悤�₭�@�g�̗��������t���܂����B�@�g�͌[�֏��̊����Ɋ��S���A�w�V���ɐ悿�V���̌�������������ƌJ�Ԃ��^���x�A�O�S���̐����Ă������A����ɓy�Y�Ɂu�w��̂��T�߁v��S�����Ă��ꂽ�����ł��B
�@�u�[�֏���Ӂv�́w�m�_�H���n�x�����^�X�x�́A�u�w��̂��T�߁v�́w�l�̏�ɐl�����炸�E�E�E�x�Ɠ������̂ł����B�@�g�́A����������A�����Ɠ����l���Ŏ��H���Ă���Ɗ������̂łł��傤�B
�@�@�ېV�̃����`�����X
�@�@�g�̐����ɓ��������̊w���ے����A�����ܔN�Z���ɕ����Ȃ�K�₵�āu�[�֎Б�Ӂv�������܂����B���̂Ƃ��A�w���Y�̑쌩�Ɋ��S����x�Ƃ̂��Ƃł��B���̕����Ȃ́A��P����̔����Ɂu�w���v�z���܂����B�u�w���v�́A�@�g�́u�w��̂��T�߁v�Ɠ����_�_�ɗ����A�l�̎���E�Ɨ��̐��_�сA���w�I�Ȋw������サ�܂����B
�@�u�[�֏���Ӂv�ɁA����A���̕�Ⳃ��t�����܂����B�w�E�E�E�w�������j�˗��Z�X�V�e�l�������m�[�����J�L�A�������w�Z�ݗ��m��b�����c�E�E�E�x�B�����Ȃ�����́u�w���v�ɂ��A�[�֏��͏��w�Z�ƂȂ�܂����B�����đS���I�ɂ��A�����Z�A���A���N���납�珬�w�Z���������܂��B���̎w���͂���܂������A�����̂悤�ɍ�����̕⏕�������ł͂���܂���B���Y��̌[�֏��Ɠ����悤�ɁA���l���������o�������Đ搶���ق��A�Ƃ̗�����肽�菬�������������肵�ď������܂����B����͂��傤�ǃA�����J�̐����J���b�������Ċw�Z���������Ɠ����悤�ɁA���́u�����v���ɂ��w�Z����̏o���ł����B
�@�@���̎����A�V��������̓����Ɋ��҂��A�e�n�ŋ����ď��w�Z�������A���{���̑��X������オ��܂����B��\�l�͂ŏЉ���悤�ɁA�����ƂɊ肢�����߂Ė��������a�V�ȍZ��������A�����̋@�^���M�����Ƃ��ł��܂��B
�@���������̌�A�w�Z����͑�\�l�͂ŏq�ׂ��悤�ɍ��̊֗^���[�܂�A�S�����ꂵ�ďW���I�ɐi�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�@�x�X�g�Z���[�u�w��̂��T�߁v
�@��@�g�́u�w��̂��T�߁v�́A�����I�Ȕ��s���������܂����B���ł����ŁA�U�ł��܂ߓ�\���B�����̐l�����O��ܕS���l�Ƃ���A�S�Z�\�l�Ɉꕔ�̊����ł��B�����ł����A����ȃx�X�g�Z���[�͂Ȃ��ł��傤�B�u�l�̏�ɐl�����炸�E�E�E�v�́A�����Љ��̒E�o�ɑ傫�ȗ�݂ƂȂ������Ƃł��傤�B
�@��ɂ��b�����悤�ɁA�@�g�́u�_�̎u�v�����w�܂�̕��Q�Ƃ��Č����܂����B�����āA�������N�ꌎ���s�́u�w��̂��T�߁v��l�҂́w�w�҂̐E����_���x�̒��ŁA�w�҂̎p����ɗ�ɔᔻ���܂��B�@�g�������ɁA�w�҂͐��{�Ɋ�肷����A���ɏA�����Ƃ���l���A���ɂ����ēƗ����ĕ������Ƃ��Ȃ��B�����āA��������ɂ����̋����K�v�ŁA�܂��܂����������Ȃ��Ă���B
�@�E�c���Y�������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B�ނ̖��I�c�@�ݗ����������_�̒��ŁA�ˎ��̂���҂͊F���ɂ���A���邢�͊��E�����߁A�����֓����ւƏW��B����ł͒n���ɂ����āA�n���̔��W��q�ǂ��̋���ɐ�O����҂����Ȃ��Ȃ�B����ł͂����Ȃ��̂ŁA�����͓����ɍs�����A���ɂ����Ċ撣��B
�@�E�E�E���̍�����A�����匠�A�������S�A�����哱���n��܂��B�@�g�͂����������̌X���ɋC�t���A�x�������̂ł����B
�@�@�����Ɩ����Ɗ����@
�@���̗@�g�ɔ��_����w�҂�����܂����B���@�w�҂̉����O�V�ł��B
�@�ނ͖������N�O�����s�́u���Z�G���v��ɘ_�����ڂ��āA�w�҂����ɏA���ĉ����������A�Ɛ�Ԃ��A��l�����A�l���́u���R�v���߂���̂���肾�A�Ƙ_���܂��B�@�����O�V�́A�l���̎��R���߂���̂ŁA����ɉ�����āu�����v���キ�Ȃ�A���̂��߂Ɋ��̎w�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����̂ł��B
�@�Ƃ��낪���̉����O�V�́A�������N�\�����s�̖��Z�G����\�Z���Ɂu�y�����{�v�Ƃ����_���\���Ď��̂悤�ɘ_���܂��E�E�E���{��������閧�ɂ�����A�l�����ق����܂܂ɐ������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�l���̗͂́A���Ȃ킿���{�̗͂ł���A�w�l���͖{�ɂ��Đ��{�͖��Ȃ�Ȃ�A���ɂ��Ė{��Y��A���������Ė{��������Ɨ~����A���͗����A���̐��S�������x�A���̂悤�Ȑ��{���w�y�����{�x���Ƙ_���܂��B
�@�����ŌE�c���Y�̓o��ł��B
�@���́w�y�����{�x��ǂE�c���Y�́A�����O�V���O�X���猾���Ă��邱�ƂƖ�������Ǝw�E���܂��B�����āA�u�����v�Ɓu�����v���������Ă���ƌ����܂��B�����O�V�����̎��R���߂���ƍ���ƌ����ꍇ�́u�����v�ł͂Ȃ��āu�����v�ł���A�u�����v�ɑΛ�������̂ł��B����ɑ��āu�����v�Ƃ́A���̑����I�ȗ͂ŊO���ɑ�����̂ł��E�E�E�����O�V�������u�y�����{�v�Ƃ́A���̖{�ł��閯���ア���߁u�����v���낤���Ȃ�ꍇ�ł��B
�@���̋�ʂ͑�ł��B���̓Ɨ����l����ۂ̔��f��ɂȂ�܂��B�u�����v���@���ɋ����Ă��A�u�����v���ク����̓Ɨ��͕ۂĂ܂���B
�@���̔��f��́A�u�n�������v���l�����ł��d�v�ł��B
�@�u���������̐����Ȃ��B�v�Ƃ����ꍇ�̒��́u�����v�ł��B���̐��f����u�����v���ۏႳ��Ă��Ȃ���A�����͐��藧���܂���B�����悤�ɁA�����̂ɔ@���Ɍ���������������Ă��A�Z���̊肢�����f�ł��Ă��Ȃ���A�u�����v�Ƃ͌����܂���B
�@���̔��f��́A�n���������l����ꍇ�̊�b�Ƃ��āA���͂́u�Z�������ƒc�̎����v�ł��b���܂����B
�@���������A���N���ɂȂ�ƁA�������{���猧�ɔh�����ꂽ�����ɂ���āA�����W���I�ȍs���������i�߂�����܂����B�����āA���������炿�������u�n�������v�́A���{�̎P���ɑg�ݍ��܂�A�@�\�������čs���܂��B
�@�E�c���Y�́A�p�˒u���ɂ���Ĕ˂��ꂼ��̓Ɨ����������A�������{�̒n���s���̐��ɑg�ݍ��܂�A���{���C���������߂��͂��ߊ����̂��ƂŐ��{�̎{���i�����̂�ڂ̓���ɂ��āA���̖���g�߂Ɋ������ɈႢ����܂���B
�@�@�@��������
�@�@�k�j���R�m���_�@
�@����}���قɁA�u���R�����v��ꊪ������܂��B������N�̏o�łł��B�����̕\��́A�hOn Civil Liberty And Goverenment "�ł��B�����Łu���R�����v�Ƃ́A���ځu�n�������v���w���̂ł͂Ȃ��u���R�ȍ����ɂ�鐭���v�Ƃ����Ӗ��ł��B���̖{�̒��҂́A���[�x���Ƃ����h�C�c���܂�̖@���ƂŁA��ɃA�����J�̑�w�ŋ������߂܂����B
�@�����āA���̖{��|�ďo�ł����̂́A��L�̉����O�V�ł��B
�@�����O�V�́A���̖{�̖`���ŁA����ƒ��҂��Љ�Ď��̂悤�ɋL���Ă��܂��B
�@���[�x���́A�w�c�ƕė����l���m���ԃj���`�E�E�E�������������Z�V�������m�}��l�m�@�N�E�E�E�x�B�����Ă��̏��́A�w�E�E�E�����m�@�L�n�k�i��������j�j���R�m���_�m�~���ȃe��|�g�׃T�X�E�E�E�x�B
�@�Ƃ��낪�����O�V�́A�u���R�����v�̑�ꊪ�̖����Ɂw�S��\���ǁX�����x�Ə����Y���Ă���ɂ�������炸�A��ȍ~���o�ł��Ă��܂���B����͂Ȃ����E�E�E
�@�����O�V�́A�|��o�ł�r���Ŏ~�߂����R����Ɍ����Ă��܂���B���̓_�ɂ��āA�����O�V���������ꂽ�g�c�D��́A�����u�����O�V�Ɓw�O�V���`�x�ɂ��āv�̒��ŁA�������}�i�I�ŁA�����̎v�z�ƕ������Ȃ��������炾�낤�Əq�ׂĂ��܂��B
�@���̕ӂ�̎���𗝉�����ɂ́A�����O�V�̗��_������ƂƂ��ɕω�������m��K�v������܂��B
�@�@�X�C�X�͖��������̐���
�@�����O�V�́A����@�g������ΔN���ŁA�ꔪ�O�Z�N�i�V�ێ��N�j�̐���B�ނ́A�����ېV�����O�̑������̗��������r���ꔪ�Z��N�i���v���N�j�ɁA�X�C�X�́w���������x�̐��̂ŁA�w����̐��M�������Ĉꍑ�x�ƂȂ闝�z�̍��ł���A�w���̌����Ȃ邱�Ƃ͐��̂̉E�ɏo������̂��炸�x�ƁA�A�����J���O���ƂƂ��ɍ����]�����Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪�����ɂȂ�ƁA��]���āA�����N�吧���Ƃ��咣���܂��B�����āA�ߓn�I�ɂ͐�ΌN�吧���]�����܂��B���̂��Ƃ��́u�^����Ӂv�i�����O�N�j�̒��ŁA�w���܂��܂������J�������ɐi�܂����āA�Ȗ��̑������ł́A�������̂𗧂ĂĂЂ낭���c�`�_����肽�Ă��Ƃ��낪�A��������̋c�_�݂̂ł������Ď����̊Q���Ȃ��ł����邩��A���悤�ȍ��ł͂�ނ��Ƃ��������炭�ꎡ���̐��̂�p���āA���R�b���̌��������������Ă����˂Ȃ�ʂ��Ƃ�����ł�����x�Əq�ׂĂ��܂��B
�@�u���R�����v�̒��҃��[�x���́A�����N�卑�h�C�c�̖@���Ƃ�����A���̏��͗����N�吧�F�������̂Łw�k�i��������j�j���R�m���_�m�~���ȃe��|�g�׃T�X�x�Ǝv���Ė{���Љ�����̂́A�|�邤���ɃA�����J���̎��R����|�Ƃ�����̂ł��邱�Ƃ������������߁A��ꊪ�ŏo�ł��~�߂Ă��܂����̂ł����B
�@�����O�V������@�g���A�ېV�̑O���琢�E�ɖڂ��J���A���R����̍������邱�Ƃ�m��A�����̍��ɗ��z�����߂܂����B�Ƃ��낪�A����@�g�����Ԃɂ����Ă��̗��O�����������̂ɑ��āA�����O�V�͎I�ϔO����������A�������{�̏����ɉ����Đ��̗��ߎ撲��p�|�̐E�ɏA���A�Ȍ�A���{�̗v�E���o�ē�����w�̏���w���ɂȂ�܂����B
�@���{�̂��̌�́A���������́u�L����c�������@���@���_�Ɍ����ׂ��v�̗��O����ނ��āA�����O�V�炪�咣����ꐧ���Ƃ̓�����ނ��ƂɂȂ�܂��B
�@�����A�����O�V�����͔͂Ƃ����h�C�c�̐�ΌN�吧�ɂ��ẮA�ǂ��ďЉ�܂��B
�@�@�j��������������
�@�������N�ɁA�_�ޏ��炪�u���I�c�@�ݗ��̌����v�𐭕{�ɒ�o���A������߂����Đ���ɘ_�c����܂����B
�@�������ɂȂ邽�߂ɂ͉��Ăɕ���Ė��I�c�@�����ׂ����B�u�L�N��c�����V���@���_�j���X�w�V�v�̎��H���B����͂��邪�o���݂Ȃ�����シ��Ƃ����_�ɑ��āA�����O�V�͎��������_�������܂��B���{�l�͖��I�����郌�x���ɒB���Ă��Ȃ��A�u�j���������������v�悤�Ȃ��̂��A�Ƃ����̂ł��B�����āA�I�ꂽ�c�������n������A���̂悤�ȋc���ɂ��c���͋�_�ɉ߂��Ȃ��B��_�ł����I�c�@�Ō��܂�ΐ��{�͎��{���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ςȂ��ƂɂȂ�A���ʂ͋��炪��Ǝ咣���܂��B
�@�E�c���Y���A���������_�������A����̏[�����咣���܂����B�ނ́A�����l�N�ɁA�ނ̏Z�ވ������ő�c�l�̑I�������{���܂����B���̂��낢��Ȗ����������邽�߂ɁA��c�l�̕K�v���������̂ł����B�������A�I�������{����ɂ͋�J�����悤�ł��B�ǂݏ������ł���l�͌����Ă��܂����B����ł����I�Ɏ��{���āA���̑��ɂ��������Ă��܂��B���̌o������A�E�c���Y�́A���̂悤�Ȕ͈͂Ȃ�I�����\�����A���̖��I�c�@�̂悤�ɔ͈͂��L���Ȃ�ƁA��s���n�炸�A�N��I�Ԃ����f���邱�Ƃ������ƍl���܂��B���ʂ́A�������܂��[�֏����[�����ċ���𐄐i���ׂ��ƍl���܂����B�����āA�n���̗D�G�Ȑl�ނ����I�c���ƂȂ��ē����z������̂������܂����B
�@�@���R�������N�@
�@�Â����Ƃł����A���a�\���N��NHK��̓h���}�ŎR�c���ꌴ��́u���q�̎���v�����f����܂����B���������������镽���L���Ɖ������������銠�J�Ì�����l���ł��B��l�́A�����ېV�̑傫�Ȏ��̗���ɖ|�M����܂��B�����čŌ�̏�ʂŁu�����v�̖�肪���グ���܂����B
�@�����ɉ�Âœ����R�Ɛ���Ĕs�ꂽ�����L���͗��ꗬ��Ē��������Ɋ������܂�܂��B�����ĈꝄ�ɉ����A�Ō�ɂ́u���R�������N�v�̊���g���ēG�w�ɐ荞�݂܂��B
�@���J�Ì��͐��{�̖�l�ɂȂ�A���{�̒����ɂ����Č��@�̑��ĂɌg���܂��B�����āA���@����̔C�ɂ������ɓ������Ƙ_�c���܂��B���̃V�i���I����A
�w�ɓ��u���Ԃ̈ӌ��Ɏ��]�����v
�@���u�E�E�E�E�E�E�v
�@�ɓ��u�ǂ��������A���{�̌����I�ɏグ�����z�_���肾�B�v
�@���u�E�E�E�E�E�E�v
�@�ɓ��u�t�����X�A�C�M���X�̎��R�����_�����ȋʏ��Ƃ��A���R�ƌ������悱���A�ŋ������点�B�{�C�œ��{�̏������l���Ă�����̂́A�܂������Ȃ��I�v
�@���u�E�E�E�E�E�E�v
�@�ɓ��u�z��ɓ��{���܂�������A�ǂ��Ȃ邩�ˁH����A�z��ɂ͖{�C�œ��{��������C�ȂǂȂ��̂��B�v
�@�Ì��u�ł͌��@�́A���R�����_���ǂ̂悤�ɁE�E�E�E�E�v
�@�ɓ��u���ɂ����v
�@�Ì��u�́H�v
�@�ɓ��u���{�̍����͂ˁA���J����v
�@�Ì��u�͂��@�i�������������j�v
�@�ɓ��u�܂����R�⌠�������قǁA���n���Ă��Ȃ��v
�@�Ì��u�E�E�E�E�E�E�i�Ռ����������Ă���j�v
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x
�@��l�����������J�Ì��́A�����̗��z�̌��@���Ă��������߁A���ق̕�����ɏo�Ȓ��̈ɓ������ɓ͂��悤�Ƃ��Čx���Ƃ��ݍ����ɂȂ�܂��B
�w�Ì��u��킭�A�����̎��R���������{�Ƃ�����{�����@����Ƃ��E�E�E�E�v�@�x
�@�������тȂ���A��Ƃ̍Ŋ��𐋂��܂��B
�@���ǁA���{�́A�v���V�A�i�h�C�c�j�̐ꐧ�I�Ȍ��@��͔͂Ƃ������@�𐧒肵�܂����B
��\��́@�@���߂ɂ���閼�]�Ǝx�z
�@�@���߂̔��ȁA�������@
�@�������{�͒����W���̐���~���܂����B
�@���ˑ̐����ŁA�u���v�ƌ����Δ˂ł����B���{�͔˂ɑ��ċK�����|���܂������A�����I�ɂ͔˂ɗ����Ă��܂����B�����ɂ��˂ɋ��͋��S�����A������y�؎��ƂȂǂ����{�����܂����B���̓_�͍����Ƃ͋t�ŁA�����I�ł����B�˂ɂ����Ă��A�ˎ�̌����͋��͂ŕ����I�ŁA���ɑ��Ĕ˂ւ̒����Ǝ��f��������߂܂������A���͉����̔N�v��[�߂�������A�����̂������̂��Ƃɂ��đ��ɔC����Ă��܂����B�˂͔N�v���Ƃ邾���ŁA�����̂悤�Ȍ��Ԃ�̎{��͂Ȃ������̂ł��B���̉^�c�͈ꕔ�̗L�͎҂𒆐S�ɍs���Ă��܂������A�_�n�̏W�ς͖����B�ȏ�Ԃɂ���A���̔N�v���W�߂�ɂ͑��l�̋��͂��K�v�Ȃ��Ƃ���A�L�͎҂̈���I�ȉ^�c�͂ł��܂���ł����B
�@�Ƃ��낪�������{�́A���ߑ̐��̂��ƂɑS�Ă̌����𒆉����{�ɏW�߂܂����B�����Ēn���ɂ́A���{�̒n���@�ւƂ��Č���z�u���āA���{�C���̌��߂�h�����܂����B�����ɂ͑�揬�搧��~���A�]���̑召�̑������ĊT�ˌ܁Z�Z�˂�����Ƃ��A�������̏���̏�ɑ���z�u���A���߂̎w�����ɒu���܂����B
�@���̂悤�Ȉ���I�ȑ̐��ɑ��āA���{���ł����Ȃ̐����o���悤�ł��B
�@�Ⴆ�Α�v�ۗ��ʂ́A�����\��N�Ɂu�n���V�̐��������V�V��\�v����b�O�������ɏo���A�u�E�E�E����������R�Ƃ��A���k���I�N���A�n���̈��J���W�Q����Ă���̂́A���{�̐��悭�Ȃ��̂ł��Ȃ���A�{�������̍s����r������Ȃ�����ł��Ȃ��B�n�������Ɋւ��邱�Ƃ����ׂĒ������{�̌����ɂ����߁A�n���ɓƎ��̌����������Ȃ��������߂ł���B���̎d�g�݂ł́A�˒��������߂����A�����܂��������{�̍߂Ƃ������Ƃɂ���Ă��܂��B�����A�n���ɉ�c���J�����̓Ɨ����������������Ȃ�A�����̐������Z�������̐ӔC�ƂȂ�A�������{�ɉ��݂����悤�Ȏ��͂Ȃ��Ȃ�ł��낤�E�E�E�v�i�哇���Îq���u�����̂ނ�v�j
�@�،ˍF����A�����\��N�̓����Ɂu�E�E�E�����̌`����@����ɁA�_�Ȃ菤�Ȃ�m�Ȃ薞�V���F�s���̂��̂̂݁E�E�E�����������ӂȂ���̂͊�������Ȃ�E�E�E���{��Ӌ���袁i�����j�̎����s�@�A���S�N�̊��K��s�ځA�\�f������̕s���A���ɐ��{�͐l���̐��{�����ӂ����ӂ��̂���Ɏ�����E�E�E�v�i�哇���Îq�������j�ƋL���Ă��܂��B
�@�����W�������A�����D�ʂƂȂ������悭������܂��B
�@�@���P�Y�Җ��P�S�@�@
�@���̂悤�Ȕ��Ȃ���A���{�͑�揬�搧��p�~���ċ����̒�����F�߁A�n���ł�n�������̓Ɨ���F�߂�ƂƂ��ɁA���I�������˒��I�ɂ��A�c��c���̑I�����F�߂܂����B�܂����B������u�O�V�@�v�ƌ�������̂ŁA�����\��N�̂��Ƃł��B
�@�������A�I�����͓y�n���L�҂Ɍ����A�N���N�ɓ��[��������������L�����[�ł����B�����āA�˒��̋����͂킸���A�c���͖����ł����B�]���Ă��̎��Ԃ́A�u�����\�O�N��������ߗ��R���v�ɂ��ƁA�u�E�E�E�e�n���m�i�����ʊσX���j�A�����悻�˒��g�i���҃n�A�������j���]�A���ҁA���n�ˊ��O�j�������ҁA���n���ƃj�V�e���փj���d�Z�����T�҃j�V�e�A�Ń����������l���m�㗬�j�����ҁE�E�E�v�i�哇���Îq�������j�Ƃ���悤�ɁA�˒���c���͈ꕔ�̗L�͎҂Ɍ����Ă��܂����B
�@���̔w�i�ɂ́A�������{�̓y�n������܂����B�������{�́A�܂����߂ɌːА��x�𐮂��A�y�n�����Ēn���s���A�y�n�����̎��R��F�߂܂��B���̌��ʁA�o�ς̌������œy�n���ꕔ�̒n��ɏW�ς���A�n�傪�������������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��܂����Ɍo�ϊ�Ղ�u���ق��Ȃ������̉��ŁA�y�n���܂��܂�����������십���̎Љ�ɋt�s�����̂ł����B
�@���̂悤�Ȏ��Ԃ𐭕{�͐��F���܂��B�����\��N�́u�n�����i�{���߁j��c�T���^��v�ɁA�u�P�Y���L�m�l�n���P�S�A���R�g��V�A���������}�����v���������ҁA���X���̓A���m�l�j���e�V���v�i�哇���Îq�������j�Ɣ��������Ƃ���܂��B
�@���́u�P�Y�����l�A�P�S�����v�́A�Ўq�́u�����_�v�ɗR�����܂��B�͕ʖ��Łu�E�Ђ̋����v�Ƃ������܂��B�ɂ́A���������l��������ɂ���Ƃ��������悤������܂���B
�@ �s��������
�@���������ɍ��̏d�����{�ɑ��āA���R���������߂銈���������ɂȂ�܂��B�����\�ܔN����\���N�ɂ����Ď��R�����^�����u�����܂����B�O�͂ŏЉ�����������╟�������A���c�����A���g�R�����Ȃǂł��B
�@�����̎��R�����^���͂�������s�k���܂����A�����̐i�W�ɕs�������������{�́A�����\���N�ɁA�����̊ē����̂��ߒn���s�������ĕҐ�����ƂƂ��ɁA�Ăь˒������I�Ƃ��܂����B���̎��ɏo���ꂽ�u�˒����I�j�t�P���S���v�ɁA�u�˒��n�i���x�N�@�i�N�������j���Z�V�@���]���Y���L�X���҃j�c�C�e�I�C�X�x�V�v�Ƃ���܂��B�O�f�̑哇���Îq���u�����̂ނ�v�́A�u�E�E�E�n���̖��]�Ƃ����Ƃ̎x�z�@�\�̂Ȃ��ɂƂ肱�݁A�ނ��n��Љ�ɂ��M�����ƌ��Ђ𐭎��ɗ��p���悤�E�E�E�v�Ƃ������̂Əq�ׂĂ��܂��B
�@���̂悤�ɂ��Ĉ�U�͊��I�ƂȂ�܂����B���������̌�A���{�����ł����O���̎������x�̌������i�߂��A���I�ł͗�������ڎw�����Ƃ��Ăӂ��킵���Ȃ��Ƃ̔��Ȃ����������̂ƌ����܂��B������\��N�Ɍ��@�����z����܂����A����ɐ旧���Ė�����\��N�Ɏs���E�����������肳��A�Ăі��I�ƂȂ�܂����B���̐���ɍۂ��Ď����ꂽ�u�s�����������R�v�ɂ́A�n�������ɂ��ĐϋɓI�ȗ����̎p����������Ă��܂��B
�@�܂��A�u�{���m�|��n�@�����y�ѕ����m���������{�Z���g�X���j�݃��v�Ɛ錾���܂��B
�@�����āA�ېV�ȗ��̏W���I�Ȓn�����x�Ȃ��āA�u�E�E�E���{�m�������n���j���C�V�@���l�����V�e�V�j�Q�^�Z�V���@�ȃe���{�m�ɎG���ȃL�@���Z�e�l���m�{�����s�T�V�����g�X���j�݃��E�E�E�E�l���n�����m�ӔC�����`�@�ȃe�ꃉ�n���m���v���v���m�S���N�X�j�����V�@�W�i�������j�l���Q���m�v�z���B�X���j�]�q�@�V�����p�V�e�n���m�����j���K�Z�V���@�{���m��Ճ��m���V���@�Q�i�悤��j�N�����j�C�X���m���̓��{���Z���g�X�B�@�����������m���j���e�@���ƕS���m��b�����c���m�����^���E�E�E�v
�@�W���̕��Q��̌����A�����̐i�n���������w��Ŏ����̑���𗝉��������@�҂̐S�ӋC���`����Ă��܂��B���A�[���Ȍ����̎��Ԃ��Ȃ������ɓ�������A�u�n�������̖{�|�v�ƌ��������ŁA�`����ƂȂ������s�̒n�������@�����a�V���������܂��B���̍��̎w���ɂ́A�n�������ɎQ�����邱�Ƃɂ���āu�����j���K�Z�V���@�{����Ճ��m���V���v�Ƃ������p�����������܂���B���̌��ʁA�Ⴆ�A�Ŏ��������Čo��ɏ[�Ă鎩���̑̌������n�Ȃ܂܍��̕⏕���Ȃǂ̎x�o�ɗ���A���̍�����j�]�ɒǂ�����ł��܂��܂����B
�@���̂悤�ɒn�������ɗ������������s���������ł����A���̗��O�Ƃ͗����ɔ��Ɍ����������I�����̗p���܂����B����́u�����I�����v�ƌ����āA�����ő��z�̔�����[�߂邲�������̍��z�[�Ŏ҂��ꋉ�Ƃ��ċc���̔�����I�сA�c��̍��œ�~�ȏ�̔[�Ŏ҂��Ƃ��Ĕ����̋c����I�ԂƂ������̂ŁA�������I���ɓ����Ă͓̎҂���ɑI�����A���̌��ʂ����Ĉꋉ�̎҂��I������Ƃ������̂ł����B�s���ł́A�X�ɎO���ɋ敪���čs���܂����B
�@����قǒn�������ɐϋɓI�Ȏp�����������s�����������A�Ȃ��A���̂悤�Ɍ�ނ��������I���������̂��B�u�s�����������R�v�̒��ŁA�u�E�E�E�s�������ȃe�������j���Q�m�W���L�Z�U�����q���Y�m�����j���C�X�������~�Z�U���K�׃��i���E�E�E�v�A�����ē����I���ɂ��āA�u�����m�������ȃe���Y�ƃ��}�}�X���m�����ƃ��L�J�̃j�E�E�E�E�ז��m�����j���Z�����T�m�����h�O�E�E�E�v�Ɩ������Ă͂���܂���ł����B�܂��A�����A�����A�c���́u���_�E�v�Ƃ��A�����Ƃ��Ė����Ƃ��܂����B���̗��R�Ƃ��āA�u���������m�y�J���U���`���i���n�@���Y�A���҃j��T���n�V�j�C�X���R�g�\�n�X�E�E�E�v�Ƃ��Ă��܂��B
�@���̌�A�I���̐����͒i�K�I�Ɋɘa����A�吳�\�ܔN�i����Z�N�j�Ɏ����Ă悤�₭��\�ˈȏ�̒j�q�ɂ��I������������̂ł����A�����ɒx���n��Љ�͖��]�Ǝx�z���蒅���A�n�������͂Ў�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂����B
�@�u�Ɓv���x�@
�@�Љ�𐧖�_�n�̏��L�҂́A�l�Ƃ��������A�ނ���u�Ɓv�ł����B�Ƒ��́u�Ɓv�ɗꑮ���A�����ɓ����܂��B�_�n����������A�u�Ɓv�͕n�����Ȃ�A�ł����Ȃ��Ȃ�Ύx�z�҂͍���܂��B������A��q�ɂ��ꊇ�����܂�Ɠ��������@��̐��x�ƂȂ�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�����u�I�̐�v
�i�L�q�̕��������M�E�C�����邱�Ƃ�����܂��B���e�͂��������B�j
���\�́@�@�h�C�c�̎���
�@�@�@�@�@�@�@�@�����̎��@
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�[�e�̔Y��
�@�@�@�@�@�@�@�@�����̐��_�̔|�{
�@�@�@�@�@�@�@�@�U�����ꂽ������`�@
�@�@�@�@�@�@�@�i�`�X�Ǝ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�`���̎����̕����@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�ȕ�������ޕ����Љ�
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W�֑����@�@�@�@�@�ڎ��֖߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������璼�ځA�n���������m�������g�b�v�y�[�W��