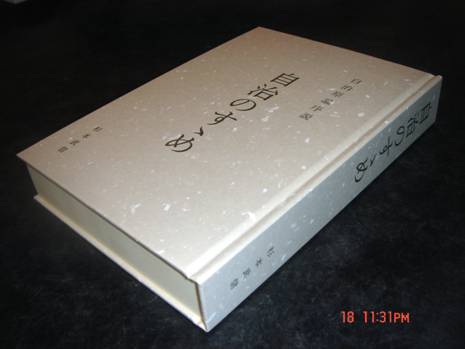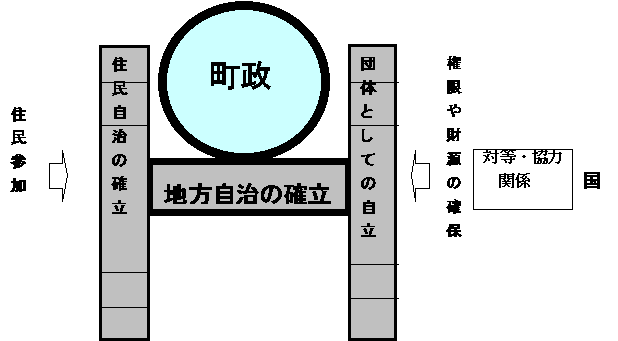
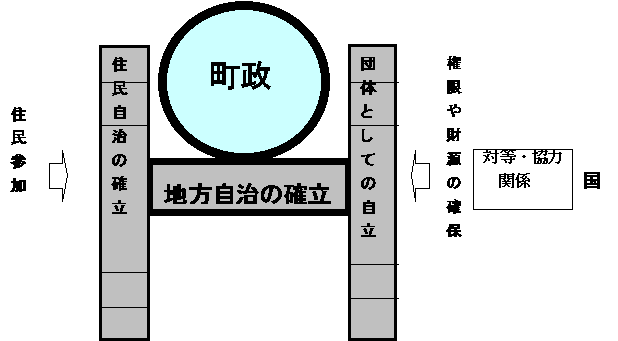
Vol.1 と Vol.2 でお示しした図です。

地方自治が確立するためには、次の二つの条件は車の両輪のようなものです。
(1) 権限や財源が確保され自治団体として自立していること
(2)
住民の参加による住民自治が確立していること
前回は(1)について説明しました。今回は(2)の条件について説明します。
住民参加の自治
① 行政情報のオープン
プライバシーに関する情報など特定の情報以外は、全てオープンすべきものです。しかし、行政に壁があって、なかなか教えてもらえないことがありました。
そのため、1980年代から情報公開条例が制定されるようになり、開示請求すれば正当な理由がないかぎり、知る権利が保障されることになりました。
しかし、わざわざ役所に出向いて、文書で開示請求するのはたいへんです。
大朝町の場合、情報公開条例は昨年に制定されましたが、未だ開示請求の例はないそうです。

行政の情報は、住民のためのものです。
住民は誰でも、いつでも知りたいと思うことを知ることができる状況でなくてはなりません。
そのため、行政の方から積極的に情報をオープンする姿勢が求められるようになりました。この姿勢を行政の説明責任と言います。制度や予算・決算などはもとより、問題点やその処理過程などを進んで住民に説明しようというものです。
| この説明責任という考え方は、自治の進んだ欧米から入ってきたものです。 住民に説明して納得を得ることは、政治を預かる者の義務とされています。 既に今日では、行政が説明に不十分な時、「説明責任を果たしていない。」と指摘されるようになりました。 |
行政の基礎的な情報を一括してオープンしている町を紹介します。
鹿児島県有明町が発行して、各戸に配布している「予算と仕事」平成14年度版です。
B4版・白黒・約100ページの冊子です。
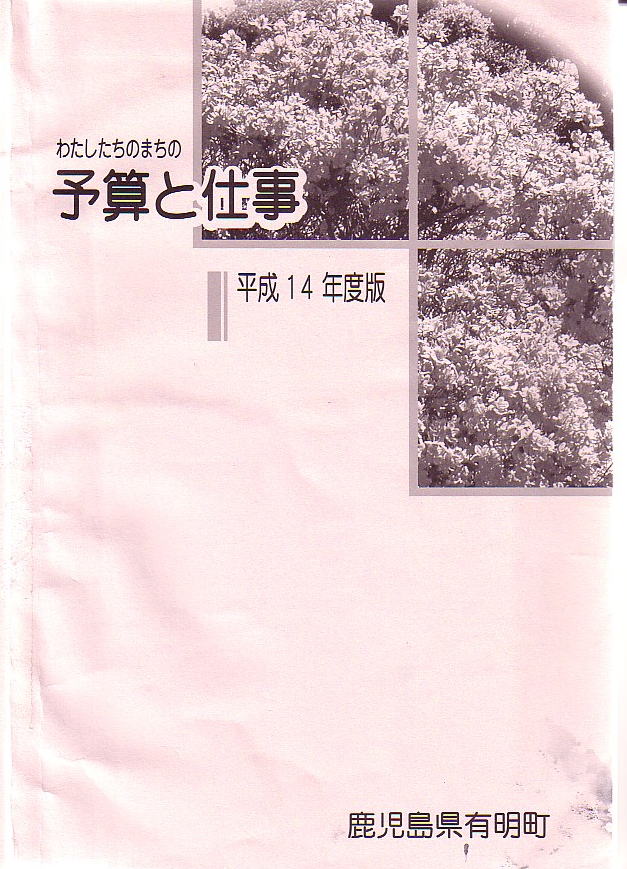
この冊子の冒頭で、冨田達次町長は、
「・・・町の予算は本来町民のみなさまのものであり、町はこの予算を分かりやすくみなさまに説明し、ご理解いただく責任を持っています。」
と述べています。
この冊子は、毎年度4月に発行され、町の事業や予算、財政状況など、町行政の全てが体系的に、コンパクトに紹介されています。
(資料)有明町の「予算と仕事」へリンク
さらに1例、66ページ下段に、農道整備工事のことがあります。
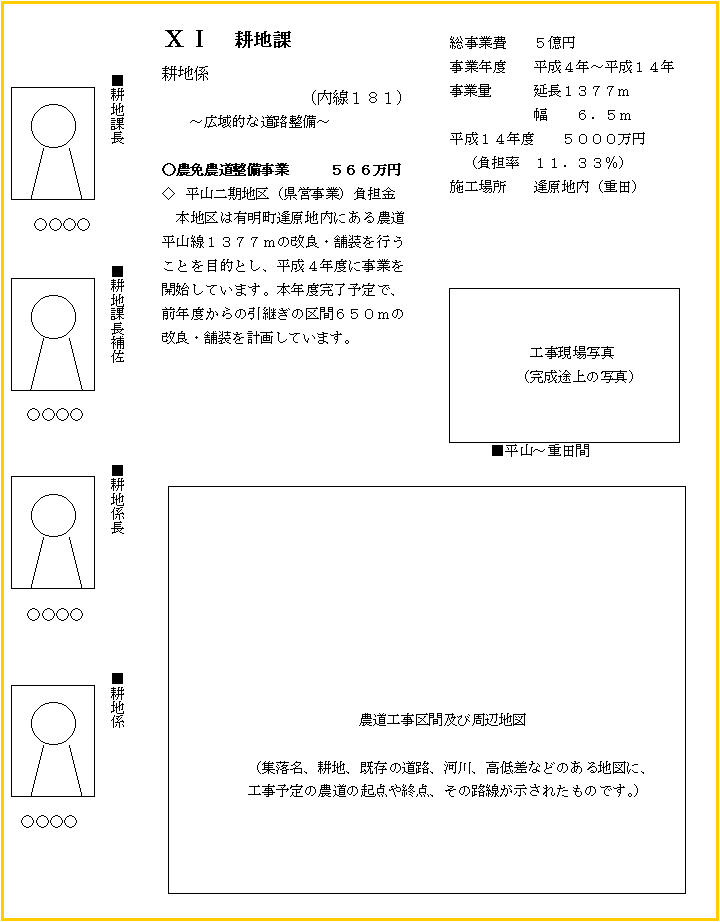
町民は、いつでも知りたい時に、知りたい事を、ざっと知ることができます。
そしてさらに詳しい事を知りたい時は、役場の担当者が載っているので、お茶の間から、あるいは職場から適宜、電話で問い合わすことができます。
さらに第二次、三次的な資料・・・例えば、次の保育所の例では、保育所の概要、運営方針、料金、送迎、等々、さらには経営状況などの資料を作成して、ロビーや行政資料室、図書館などに備え付けるとともに、ホームページに掲載すれば、もっと親切でしょう。
できれば、担当者にお願いしなくても見れる状況が大切です。
お願いして見せていただくと、負い目になり、言いたいことも言えなくなるからです
このような冊子があれば、合併の不安・・・本庁が遠くなる、担当者を探すのがたいへん、転勤で知らない人が支所にやって来た、町全体のことがわからない・・・といった場合も安心です。
工事が始っても、地権者、地元、工事関係者以外
の者には、工事のことがよく分かりません。
町内でも行かない所の工事は分かりません。
特に合併したら、「あの旧町では大きな工事をしているのに、我々の地域の要望を取り上げてくれない。」といった誤解や不満が出る恐れがあります。
もし合併後、このような冊子があれば、新町全体の工事や事業がわかり、各地区で行われているいろいろな事業を総合的・全体的に理解し、納得あるいは批判できるでしょう。
分権の時代は、受益と負担(税)を併せ考えなければなりません。
そのためには、どこにどれだけ予算が使われているか、行政全体がわかる資料が是非とも必要です。そして住民は、平素から、税金がどのように使われているか、行政全体を見る力を養わなければなりません。


年度始めに、学校は保護者や地域に、シラバス (年間学習計画)や生活指導など具体的な目標 を示します。そして年度末に、学校が自己評価 し、保護者や地域の意見を聞き、次年度に生か します。
広島県では、9月補正予算の編成過程から公開するとの方針を打ち出しました。
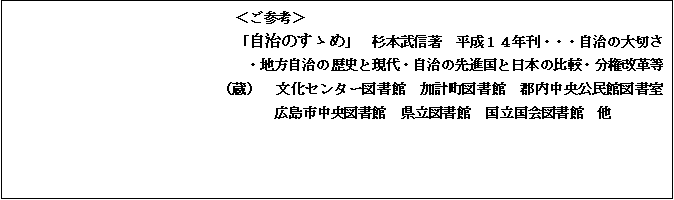
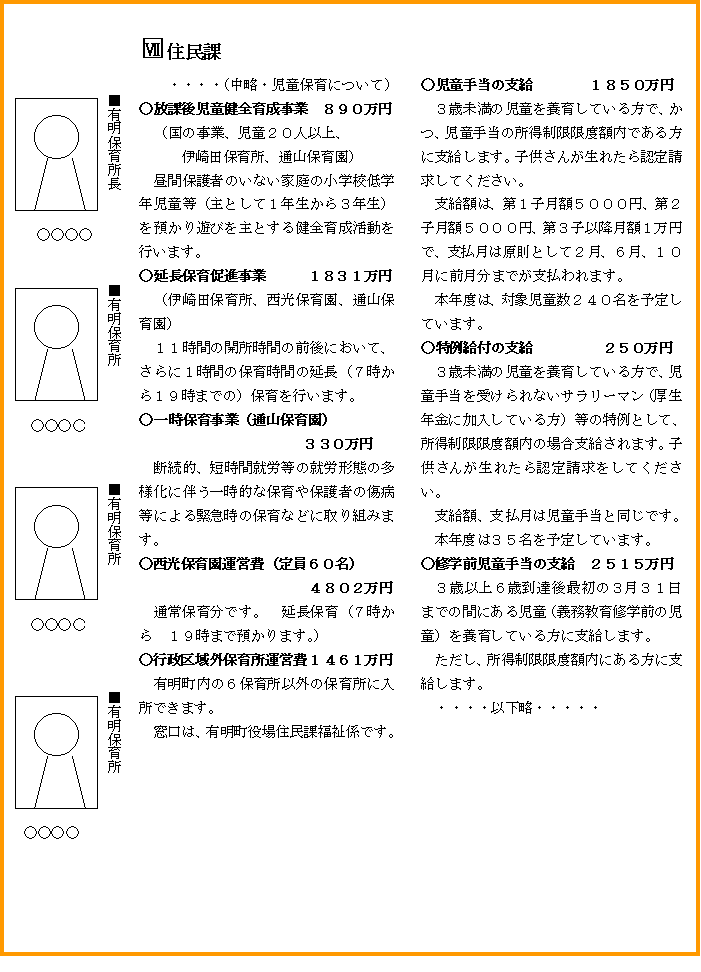
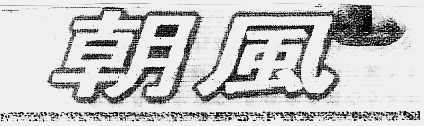
http://www12.ocn.ne.jp/~jiti2/
地方自治を確立する会
代表 杉 本 武 信
第3号(住民自治の実践)
2003・7・22